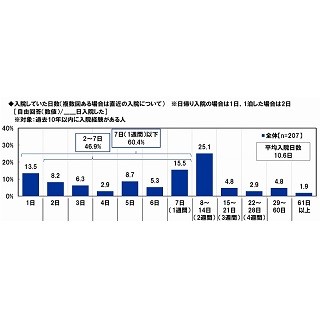国立がん研究センターによると、今や2人に1人が生涯の間に罹患(りかん)すると言われている「がん」。働きざかりの世代にとっても、もはや他人事ではありません。がんになると、仕事や家族、そしてその生活はどう変わるのか。本稿では、子どものいるがん患者のコミュニティ「キャンサーペアレンツ」の代表理事である西口洋平さんへインタビュー。がんを患ってから立ちはだかったさまざまな壁と、その乗り越え方、またキャンサーペアレンツの活動について話を聞きました。
西口洋平(にしぐち・ようへい)さん
|
|
1979年10月生まれ、39歳。2015年にステージ4の胆管がんと告知され、現在も抗がん剤治療中。2016年に一般社団法人キャンサーペアレンツを立ち上げ、代表理事を務める。小学5年生の娘をもつ。
「まさか自分ががんになるとは思ってもいなかった」
西口さんは、大手人材総合サービス会社の営業として、昼夜問わず働いてきたいわゆる「仕事人間」。働き盛りでますます仕事に邁進していた34歳の夏ごろ、体の異変を感じ始めます。最初は「疲れているのかな」と思う程度だった異変は、そのうち寝てもとれない異常な疲れ、止まらない下痢へと、進行していきました。病院で下痢止めをもらい急場しのぎをする日々が続くと、半年間で体重は約6キロも減少。さすがにおかしいと思い、胃と腸の内視鏡検査をしたものの、異常は見つかりませんでした。
診察のときに医師の目に留まったのが、西口さんの黄色くなった目。黄疸(おうだん)の症状が出ているとわかり、翌日から別の病院で検査入院することになりました。検査の結果、主治医から「悪性腫瘍の疑いがあります」と告げられたとき、西口さんは思わず「なんですか、それ?」と質問。「いわゆる『がん』です」と言われても、「まさか自分が『がん』になるなんて……」となかなか実感はわかず、だれか別の人のことのように思えたと言います。
西口さんに初めて実感が訪れたのは、入院中の病院から、地元大阪の母親に電話で病名を告げたときのこと。最初なかなか言葉が出てこず、仕事人間だった息子から平日の昼間にかかってきた電話に異常を感じ取った母親も何も話さず、数分間の沈黙が続きました。振り絞るかのように「がんでさ……」と伝えた西口さん、初めて病気になった自分を客観的に見つめ、涙が止まらなくなりました。息子からの思わぬ言葉に、母親も電話口で号泣し、父親は「大丈夫やから!」と自分に言い聞かせるかのように大きな声で呼びかけていたそうです。電話を切った西口さんはトイレでひとしきり泣いて、顔を洗い病室に戻りました。
手術では取りきれず……抗がん剤治療が始まった
2015年の2月上旬に胆管がんの告知を受けた西口さんは、それから2週間後には手術を受けました。しかし、開腹してみるとがんは予想以上に広範囲に及んでおり、すでに手術できる段階ではありませんでした。そこからは抗がん剤治療を開始。抗がん剤の副作用と付き合いながら、いかに進行を遅らせるかという西口さんの治療が始まったのです。
はじめは週に1回通院し、2種類の抗がん剤を点滴投与。しかし、便秘や吐き気、体のほてりなどの副作用が西口さんを襲いました。副作用を抑えるため、薬も使ってみては変えながら、より快適に治療ができるよう試行錯誤したそうです。その後、抗がん剤を1種類に減らし、手術から約3年間点滴での抗がん剤治療を行いました。
抗がん剤治療は主治医の想定よりもかなりうまくいったそうですが、昨年秋の検査でがんがまた進行している可能性があると指摘されました。そのため、現在は飲み薬の抗がん剤の治験に切り替えて治療を続けています。通院は3週間に1回に減り、副作用はありつつも、仕事に家庭にと、毎日の生活を一歩ずつ歩んでいます。
がんになっても仕事で「役割を担う」大切さ
がんになるまで仕事人間だった西口さんは、「勤務できる時間が減れば、戦力外になってしまうのでは」とこれまで通りに仕事ができなくなることに不安を感じ、まずは人事部に相談することにしました。人事部長は西口さんの話を淡々と聞き、治療の予定や、有給休暇の取得など、先の見通しを冷静に立ててくれたのだそうです。「感情的にならず、がんになっても会社で働き続けるにはどうすればいいかいっしょに考えてくれたことに救われました」と西口さんは振り返ります。
そこから西口さんは、週に1回抗がん剤治療の通院のため会社を休み、朝9時から午後6時までの残業なしの勤務体系になりました。「周りのメンバーは遅くまで働いているのに、自分だけ早く帰って数字も上げられない」と焦りを感じることもありましたが、今の自分にもできる経験や知識をシェアできるような仕事を積極的に見つけたそうです。
西口さんは現在も体調と相談しながら仕事を継続しています。がんになって仕事を辞めざるを得なかった人も多くいる中で、週1回の通院で、仕事への支障が限定的だったため、続けてこられたのではないかと考えています。また西口さんは、「35歳で病気になるまで一生懸命働いてきた。周りの人たちもそれを踏まえて、『あいつは裏切らない、頑張ってほしい』と期待してくれていたし、それに対して最大限応えたいと感じた。真面目に仕事してきてよかったなと、そのときは思いましたね」と振り返ります。収入は減りましたが、職場には自分の役割がある、そういった治療以外の「役割を担う」ことは、西口さんにとって精神的にも大きな支えとなっているようです。
小学4年生のときに娘ががんの本を借りてきた
がんになって最も西口さんが悩んだのは、子どもへの病気の告知でした。がんがわかったとき、娘さんはまだ小学校への入学前。病気についても、生死についても理解できるとは思えず、詳しく説明はしませんでした。「伝えるかどうか、伝えるならどう伝えるか、自分でも正解が見つからずにモヤモヤして、一旦保留にしました。元気に見える僕がまさか死ぬだなんて、娘は思いもしていないと思うと思考停止になってしまった」と思い返しました。
結局娘さんには、奥さんから病気のことを伝えてもらうことに。娘さんは一見態度は変わっていませんが、入院すると、「父ちゃんのがんが治りますように」と手紙を書いてくれました。小学4年生のときには、学校の図書館でがんの本を借りてきて、西口さんの前で「私が読んであげるから聞いておいて。勉強した方がいいよ」と音読してくれたのだそうです。「子どもなりに何かサポートしたいという思いがあるんでしょうね。彼女なりに勇気を出したのかわからないけれど、がんの本を借りるという行動には驚かされました」と西口さんは感慨深そうに語ります。
病気になるまでは、ほとんど子育てには関わっていなかった西口さん。病気になってから家族との時間が増え、旅行にも行くようになりました。「仕事はもちろんちゃんとやりますが、家族との時間は大切にしたい。子どもってすごい勢いで成長するし、最近は将来こんなことをしたいという希望も出てきて、その存在が自分にとっても励みになっています」と、目を細めていました。
がん告知後の生活について、詳細に語ってくれた西口さん。前向きな姿がとても印象的でした。西口さんの仕事や家族との向き合い方は、病気ではない人にとっても学びとなりそうです。