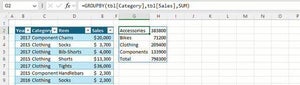55歳での処遇逓減も排除、65歳まで「第一線で働く」新制度
少子高齢化社会が進む中、労働人口の減少に伴う人手不足は企業にとって深刻な問題だ。また、公的年金の支給開始年齢引き上げもあり、社会的にも高齢者の雇用安定が求められている。従来型の定年者再雇用だけではない方策に各社が乗り出す中、TISは2018年10月に「65歳定年制度」の導入を発表した。
この制度は、ありがちな「60歳以降の再雇用を1年契約ではなく65歳までの固定にする」というものではない。その特徴は「処遇が現役時代と変わらない」ということだ。正確には、現役時代の待遇が65歳まで継続することになる。
「当社はもともと、昇格の基準に年齢や勤続年数がないなど、年齢が関係ない仕組みをとっておりました。退職金も確定拠出年金ですし、額も勤続年数に関係しない基本給基準です。そうした中で、55歳以上の処遇だけが年齢を基準にしていることに以前から課題は感じていました」と語るのはTIS 人事本部 人事企画部長 小泉靖彦氏だ。
従来の制度では、55歳の時点で専任職に職種変更を行い、職責と処遇を逓減する。逓減率は、60歳以降の再雇用希望の有無で変わる。再雇用時の処遇が現役時代から大幅に下がることもあってか、以前は対象者のうち30%程度しか再雇用の希望者がいなかったという。
「業務上、どうしても残っていただきたい方には特別に処遇をよくすることで、シニア社員を増やしてきました。しかし、そうした特別扱いはどうなのかということ、また、残っていただいたシニアの方向けに特別な職務をつくるにも限界があるということもあり、定年自体を伸ばそうと考えました」と小泉氏は語る。
TISでは3年前から、Great Place to Workの調査によって従業員にとっての働きがいを測定している。Great Place to Workは「働きがい」に関する調査・分析を行い、一定の水準に達していると認められた会社や組織を発表しているが、日本でも「働きがいのある会社」ランキングを公開している。
TISの同調査の結果だが、全体の傾向としては右肩上がりである一方、55歳以上の年齢層の2017年の結果が低かったという。専任職に職種を変更して、職責・処遇が逓減されている世代だ。
「働きがいを阻害している原因や働きがいを改善するための対応策が簡単にわかる調査ではないのですが、55歳以降の処遇制度が働きがいの向上を妨げている要因の1つとは感じていました。そこで、3月に経営サイドに定年延長について打診しました」と小泉氏。これを受けて、2019年4月から同制度の導入が決定されたという流れだ。
年齢に関係なく実力で評価される制度を導入
「現在、55歳から60歳までの職責が逓減されている方には、元の状態に戻って他の社員と同じ土俵で勝負していただきます。現在、60歳以上の方は60名います。これらの方は元のグレードに直接戻すにはブランクがあるということで、正社員に復帰いただきますが、まずはシニア時のグレードに紐づいた正社員グレードに戻っていただく予定です」と語るのは、TIS 人事本部 人事企画部 主査 三枝尚子氏だ。
後進の育成を考えてポストオフ自体は60歳に定めたものの、それ以外に年齢が問題になることはない。再雇用からの復帰者が管理職になる可能性もあるという。また、2018年から導入したスペシャリスト認定制度があり、年齢に関係なく実力を持つ人はその制度で処遇されるようになる予定だ。
「現在すでにポストについている方とスペシャリストは同数くらいいます。今後はスペシャリストが増えて行くでしょう」と三枝氏。退職金こそ確定拠出年金であるため60歳が境になるが、それ以外は58歳と61歳の差は48歳と51歳の差と変わらない意味しか持たなくなるようだ。
実力主義であるため、元々年下の上司、年上の部下という存在が社内で違和感なく存在している。年齢による衰えや最先端技術への対応の難しさはあるだろうが、それは会社側で最低限の査定をするほかは、本人の判断と働き方で対応するようだ。
「定年は60歳、63歳、65歳で可能です。衰えを感じるのならば早めに定年ということにしても構いません。そこは柔軟に対応したいと思っています。業務内容については、例えば開発は難しくても事業企画のように経験が活きる場はあると考えています」と語る小泉氏。「人手不足は大きな課題であり、すべての職種で人が欲しい状態。今回の65歳定年制度は人手不足解消に向けた施策の1つです」とも話していた。