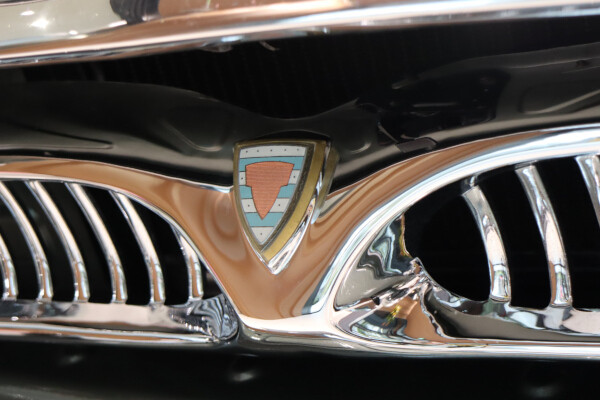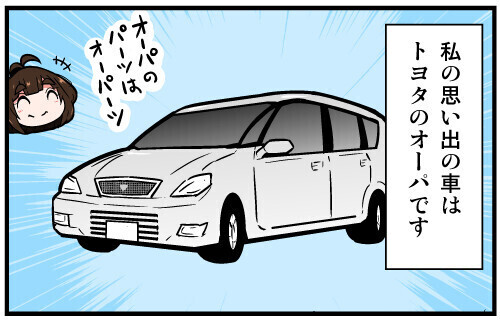長年、マツダブランドの象徴であり続けている「ロードスター」。1989年に登場した初代ロードスター(型式から“NA”とも呼ぶ。2代目は“NB”、現行の4代目は“ND”)以来、一貫してマツダが目指す“人馬一体”を体現してきたモデルだ。2019年2月の発売30周年を前に、「ロードスター」が歩んできた道のりをライトウエイトスポーツの歴史とともにプレイバックしたい。
時代に翻弄されたライトウエイトスポーツの歴史
第二次世界大戦後、世界ではモータリゼーション(自家用乗用車の普及)が進み、自動車産業が発展していった。1950年代に入ると、自宅のガレージなどでクルマを作る多くの「バックヤードビルダー」が誕生した。
バックヤードビルダーは木箱で部品をユーザーのところまで運び、ユーザー自身の手でプラモデルのようにクルマを組み立てる“キットカー”を提供。イギリスの自動車メーカーであるロータスも、もともとはバックヤードビルダーだったことはよく知られた話だ。手頃な値段でクルマを手に入れられるキットカーの興隆により、スポーツカーの楽しみは広く人々に普及した。
このように、クルマが安く手に入る土壌が形成されたこともあって、1960年代には走って楽しいライトウエイトスポーツカーが最盛期を謳歌していた。ところが、1970年代になると情勢は一変する。その大きな要因となったのが、アメリカで成立した排出ガス規正、いわゆる“マスキー法”だ。この規制は、排出ガスに含まれる一酸化炭素と炭化水素を1975年から、窒素酸化物を1976年から、ともに従来の10分の1に削減したクルマでなければ、販売を認めないという厳しいものだった。
当時は、エンジンの高回転・高出力を目指して自動車各社が開発を進めていた時代。当然ながらマスキー法の衝撃は大きく、基準をクリアするため、各自動車メーカーはエンジンの出力を下げざるを得ない状況となった。さらに、1974年には“極低速域での衝突に関して、ヘッドライトは壊れてはならない”など、衝突安全のレギュレーションが自動車保険に加わる。安全性を高めるためには、大型バンパーや衝撃吸収装置をクルマに装着する必要があった。
こうして、クルマは大きく重くなり、もともと非力であったエンジンのパワーは、さらに低くなっていった。小さく軽いため、非力なエンジンであっても楽しく走れることを特徴とするライトウエイトスポーツにとって、それは非常に苦しい時代だった。各メーカーの生産も頓挫し、この種のクルマは事実上、その姿を消すことになる。
NAから受け継がれる人馬一体のDNA
それから時代は流れて十余年後。マツダは1989年に初代「ロードスター」を発表し、もう作れないといわれていたライトウエイトスポーツを復活させた。初代ロードスターは、(1)歴史的に培われてきた伝統様式、(2)最新の技術、(3)走って楽しい正統派ライトウエイトスポーツの3つをコンセプトとして登場し、大成功を収めた。
「ロードスター」では初代NAから現行モデル(ND)まで、ライトウエイトスポーツとしてのパッケージ哲学を脈々と引き継いでいる。例えば、フロントミッドシップのフロントエンジン・後輪駆動(FR)方式や、後ろ側にキャビンが寄る特徴的なスタイリングなどがそれだ。
その中でも、歴代4モデルに共通している特徴的な点がプラットフォーム構造(ベアシャシー)だ。ここからも、マツダが目指す“人馬一体”、つまりは走る楽しさ、運転する喜びを追求する姿勢に変化がないことをうかがい知ることができる。
クルマの中心部を縦に通るパワー・プラント・フレームは、エンジンとファイナルドライブユニットをしっかりと固定する。これによりブレを抑え、アクセルオン・オフ時の反応を向上させる。また、エンジンなどの重量物をなるべく内側に配置することで、低重心化とコンパクト化を実現。クルマの回転方向にかかる慣性を小さくすることで、ヨー慣性モーメントの低減と重量バランスの最適化を図っているのだ。
こうした一貫したマツダの姿勢について、現行「ロードスター」の開発主査を務める中山雅氏は、「量産性を考えると、決して効率的なものではないと思います。ですが、『走る歓び』を体現するため、こうしたユニークな設計をしています」と語る。
新旧「ロードスター」比較!そこから見えるマツダらしさ
マツダは先日、技術説明会を開催し、「2030年に全てのクルマに電動化技術を搭載する」と発表した。では今後、マツダが大きく方向を転換するのかといえば、そうではないと思う。
電動化技術は、あくまで環境に配慮し、時代のニーズに合わせたものだ。マツダが時代のニーズに対応しつつも、“走る歓び”を追求する姿勢を捨てないであろうと信じるのには理由がある。
その理由を語るため、今回はNAとNDの“重量”を比較してみたい。カタログデータではNAが940~960kgであるのに対し、NDは990~1020kgとなっている。一見、重量が上がっているように見えるが、これにはカラクリがある。
実は、NAにはエアコンやパワーステアリング、パワーウインドウといった、現在のクルマであれば搭載されていて当然の装備が含まれていない。これらはNAの場合、オプション装備となっていたのだ。つまり、仮にこれらをNAが装備していた場合、重量はNDと同等程度になると見込まれる。
またNDは、NAの時代にはなかったエアバッグや衝突被害軽減ブレーキなどの安全装備を搭載していて、燃費を見るとリッターあたり4kmの向上を達成している。安全性と環境性能が改善しているにもかかわらず、NAの頃から重量に変化がないのは、まさに最新技術の賜物といえる。
重量比較を通じて分かるのは、NAが目指した3つのコンセプトが、30年という時を経てもNDに受け継がれており、正常進化を遂げていることだ。おそらく、この理念は「NE」、「NF」と系譜が連なっていっても変わることはないだろう。
このことからも、マツダは今後もマツダらしくあり続け、「ロードスター」はマツダのブランドアイコンとして、ますますその価値を高めていくに違いないと考えられるのだ。
(安藤康之)