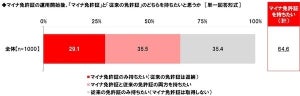電気自動車が普及するまでの運命? PHEVとは何か
メルセデス・ベンツ「EQC」やアウディ「e-tron」など、将来的に市販される電気自動車の発表が相次ぐ中、日本ではホンダ「クラリティ PHEV」や三菱自動車工業「アウトランダーPHEV」の試乗会が続いた。
そこで、NewsInsight編集部から寄せられた疑問は、「PHEVって将来性はあるの?」というもの。確かにPHEVは、EVが車両価格や航続距離といった課題をクリアするまでのつなぎの技術として有望であり、「しばらくは乗用車の主流になるのでは?」といわれているが、逆に見れば、バッテリーが進化して電気自動車が本格的に普及した時、消えてしまう運命にあるとも考えられる。本当にそうなのか考えながら、「アウトランダーPHEV」と「クラリティ PHEV」を試乗してきた。
ちなみに、プラグイン・ハイブリッド車には、PHEV(Plug-in Hybrid Electric Vehicle)とPHV(Plug-in Hybrid Vehicle)という2種類の表現の仕方があるが、電気モーター駆動がメインの電気自動車に近いという理由から、前者を名乗ることが多い。
そのほか、純粋な電気自動車はBEV(Battery Electric Vehicle)あるいはEV(Electric Vehicle)、航続距離を伸ばす目的で発電用エンジンを搭載したレンジエクステンダーEVはBEVx(Range-extended Battery Electric Vehicle)またはREx(Range-extended)、普通のハイブリッドカーはHV(Hybrid Vehicle)またはHEV(Hybrid Electric Vehicle)と表記することが一般的になってきている。BEV、BEVx、Rex、PHEV、PHVは、外部充電できることから「プラグイン・タイプ」とくくられることもある。
三菱自動車が「アウトランダーPHEV」を大幅改良
本稿ではまず、アウトランダーPHEVの2019年モデルをレポートしよう。このクルマは発売からすでに6年が経過しており、改良のたびに進化してきてはいるが、2019年モデルはフルモデルチェンジにも匹敵する内容のビッグマイナーチェンジだという。
では、なぜフルモデルチェンジではないのかというと、まずはデザインを根本的には変えていないからという理屈がある。さらにいえば、累計販売台数16万台と世界で最も売れている「プラグイン・タイプ」の同車ではあるが、ガソリン車のアウトランダーを含めても、6年サイクルでフルモデルチェンジできるほどのボリューム(販売台数の規模)を獲得できていないことも理由のひとつだ。
パワートレーンのシステムは、ガソリンエンジンが発電に徹してモーターで駆動する「シリーズ・ハイブリッド」を基本とするが、高速域ではエンジンが直接駆動するモードも持っている。
エンジンで発電した電気でモーターを駆動すると、エネルギーの変換ロスが生じて効率が悪そうなものだが、エンジンは0rpm(1分間あたりのエンジン回転数を示す単位)からアイドリングの1,000rpm弱までは全く使いものにならず、有効なトルクを発生するエンジン回転域に達するまでは力が足りない。だから、低・中速域では、トランスミッションによってエンジン回転を減速してタイヤに伝えて、駆動する必要がある。つまり、エンジンが回っている割にタイヤが転がらず、距離が伸びない(=燃費が悪くなる)。高速道路を走るよりも、街中の方が燃費が悪化するのはそのためだ。
一方のモーターは、0rpmから最大トルクを発生できるのが強みで、トランスミッションは不要。大抵のモーター駆動車は1ギアのみで、低速域ではその少ない仕事に比例してエネルギー消費も少なく、変換ロスを相殺する以上の効果があって燃費が良くなる。ただし、時速60km以上になってくると、エンジンもトランスミッションのトップギア相当で走らせられるようになるので効率は良くなり、モーターの優位性は薄れてくる。
プラグイン・タイプではないシリーズ・ハイブリッドの日産自動車「e-POWER」(ノートとセレナというクルマに日産が導入している技術)などは、エンジンが直接駆動するモードを持たないので高速域では燃費があまり良くない。日本では、それでもトータルで取り分があるが、欧州やアメリカなど、高速度域で走るシーンの多い地域ではメリットが得にくいはずだ。
シリーズ・ハイブリッドとエンジンによる直接駆動の2つのモードを持つアウトランダーPHEVのシステムは、現時点での最高効率を狙う理想的なカタチといえる。ホンダのクラリティPHEVや、プラグインではないが「i-MMD」(ホンダが“スポーツ・ハイブリッド”と表現するIntelligent Multi-Mode Driveのこと。モーターのみで走れる距離が長い)と呼ぶ技術を搭載するクルマも同様だ。
燃費よりも走りを求めた改良か
アウトランダーPHEVはパワートレーンの9割を刷新した。エンジンは2.0Lから2.4Lへと排気量がアップしている。クルマの前後に2つ搭載する駆動用モーターは、リアの出力が約12%向上。バッテリーは容量を12kWhから13.8kWhへと増やし、EV走行の航続距離を60.8kmから65kmへと伸ばした上、出力も約10%高めた。ジェネレーター(発電機)の出力も約10%上がっている。
エンジンと電気の双方ともに強化されているわけだが、ハイブリッド燃費(JC08モード)が従来の19.2km/Lから18.6km/Lへと落ちていることからも推測できる通り、今回の改良の狙いは燃費よりも、走りの質感を良くすることに主眼がおかれている。具体的にはエンジンの音・振動や存在感を抑えて、EV感を強めている。
アウトランダーPHEVに限らず、HVに乗り慣れると、モーター駆動の静かで力強い走りの気持ち良さがだんだんと病みつきになってきて、エンジンがかかると何だかガッカリしてしまうようになってくるものだが、その心理を汲み取った改良と捉えることもできるだろう。
エンジンの排気量が上がったことによって、同じ出力を求めた時には従来よりも低回転で抑えることができるし、それなりの大出力を要求する時には、スパーンと高回転に持っていかずとも、ジワジワと上げていけば済むようになった。それらは音・振動の低減に効く要素だ。ジェネレーターの高出力化は、ハイブリッドモード走行時にエンジンをかける頻度を少なくする。エンジンがかかりづらく、かかっても音・振動が少ないから、エンジンの存在感は薄れる。それにより、EV感が高まるというわけだ。
バッテリーの充電量が十分にあって、EVモードで走行している時でも、強い加速を求めればエンジンがかかる時はある。モーターの最高出力はフロント60kW、リア70kWで、合計130kW。それに対し、バッテリーから出せるのはざっくり半分の70kW程度と推測される(スペック未公表)。アクセルを床まで踏み込んでフルパワーを求めれば、モーターの最高出力の半分しかバッテリーからは供給できないので、エンジンをかけて残りを補うことになる。今回の改良ではバッテリーの出力が上がっているので、エンジンがかかるまで粘ってくれるのだが、それもEV感の高まりを感じさせてくれるポイントの1つだ。
エンジン発電・モーター駆動での走行が「シリーズハイブリッド・モード」と呼ばれるのに対し、エンジン直接駆動は「パラレルハイブリッド・モード」という。前述の通り、後者は速度域の高い欧米で戦う上で武器になる。日本でも、流れのいい郊外路や高速道路の実用燃費では、かなり効いてくる要素になるだろう。運転していても、パラレルに切り替わる時にショックを感じることなどはなくて、メーターの表示でそれと知れるだけだ。
エンジン直接駆動は、高速域で負荷が少ない領域に使用が限られるものの、ちょっとアクセルを踏んだら解除されるのではないかと経験則で推測していたのだが、そうではなかった。いったんパラレルに入れば、それなりの加速やトルクを要求しても、エンジンの力以上に応えてくれる。それは、モーターがエンジンをアシストしているからだ。だから、パラレルでもエンジンでブルブルと走らせている感覚は少なく、EV感が続いていくのだった。このクルマを実際に所有して日常的に乗れば、パラレルも頻繁に使うことになる。モードが切り替わった時のフィーリングは気になるところだが、アウトランダーPHEVは期待以上だ。
新設定の「SPORTモード」はどんな乗り味か
追加された「SPORTモード」も見所の1つ。こちらは、アクセル操作に対して素早いレスポンスが得られる走行モードで、確かに敏感で楽しかった。今回の改良の主目的とは反対に、このモードではエンジンがかかりやすくなるが、それも強大なトルクを素早く出すためであって、理にかなっている。
だが、タイトコーナーが続くワインディングを走っていると、これでも物足りなくなってきた。コーナーの立ち上がりでアクセルを床まで踏み込んでも、エンジンの回転数が高まって、モーターがフルパワーを発揮するまでにはタイムラグがあるからだ。
SUVのアウトランダーならこれでもいいけれど、このシステムでもっとスポーティーなモデルを作る時には、SPORTの上の「SPORT+」や「RACE」といったようなモードを設けて、常にエンジンを最高出力発生回転数にキープするようにして欲しい。アクセル操作に対して、間髪を入れずにポテンシャルを発揮することになるから楽しいだろう。これでは燃費が悪そうだが、限られたシチュエーションで使うだけだし、バッテリー容量が大きなPHEVだから、余剰トルクは発電して貯めておけば、そんなに効率が悪いというわけでもないはずだ。
シャシーなどもしっかり進化、内容に対して価格は割安?
そのほかにも、ショックアブソーバーの径拡大やステアリングギア比のクイック化といった改良が見られるが、中でもシャシー系の進化は見逃せない。
従来モデルでは、2017年の改良時に登場した「S-Edition」で、テールゲート開口部とリアホイールハウス周りに構造用接着剤を採用し、剛性向上を図っていたが、今回は、その範囲を前後ドア周りにまで拡大してきた。しかも、「S-Edition」のみならず、ガソリン車も含めて全車に同様の改良を施している。以前は構造用接着剤の塗布が手作業だったので、できる数は限られていたのだが、「エクリプス クロス」(2018年3月に発売したSUV)でも構造用接着剤を使いたいと考えた三菱自動車は、生産設備に投資して同工程を自動化したのだという。
基本的に、設計年次としては決して新しくないクルマであることもあって、ボディ剛性の向上は大きな効果を発揮する。路面から大きな入力があっても、ボディから安普請な音や振動を感じることがなく、サスペンションがスムーズにストロークしていた。ステアリングを通じて得られる接地感が増しており、ハンドリングが楽しくなった。とくに「S-Edition」でS-AWC(車両運動統合制御システム)をSPORTモードにすると、アクセルオンで旋回力を増していくような挙動が感じられて愉快だ。
今回、アウトランダーPHEVが受けたビッグマイナーチェンジには確かな効果があったようだ。その内容に対し、車両価格はリーズナブルといえるだろう。PHEVの将来性については次回、ホンダのクラリティPHEVの出来栄えについてレポートするつもりだから、その後にお伝えしたい。
(石井昌道)