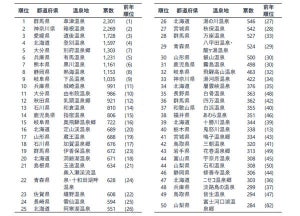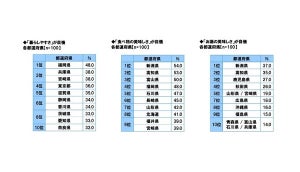5月16日、国交省は福岡空港運営権の優先交渉権者に地元連合「福岡エアポートHDグループ」を選定した。これまで幾度となく「地元連合が空港運営を続けることの是非」が話題に上ってきたが、今回初めて"地元"が選考を勝ち抜いたことが、今後残る空港民営化案件にどのような影響をもたらすのだろうか。
-
福岡空港民営化に向けた第二次審査で、福岡エアポートHDグループが優先交渉権者に選定された。6月に基本協定を締結、8月に運営権設定・実施契約を締結、11月にビル施設等事業の開始、2019年4月に空港運営事業の開始を予定している
"地元"と言っても濃淡がある
そもそも、民営化される空港の経営において"地元"は勝つべきなのだろうか。諸説あろうが、筆者は「地元が従前と変わらず主導権を持って経営を担うべきではない」との持論を持っている。
「新千歳を含む北海道7空港一括民営化における3つの心配」にも書いたことがあるが、新たな経営者と民間の知恵を導入することで空港経営を抜本的に改革しようとする民営化の趣旨に照らして考えると、これまでの空港運営のしがらみと既存概念に縛られた地元経営が民営化後も引き継がれるのでは、国への新たな負託を背負い、新たな民間の知恵を活用して経営革新が進められるとは期待できないと誰もが思うことだろう。
それを糊塗するために、一見新たなプレイヤーを加えて"今までとは違う感"をいくら演出しても経営自体が変革しなければ意味はなく、提案書にいくら新機軸が盛り込まれていてもすぐに実現への行動は期待できない。「今言うならなぜこれまでにやらなかったのか」に、まず答える必要があるからだ。
もちろん、空港を運営するのに"地元との協調・協業"は大事だが、地元企業が新運営権者としての権限を持たなくても十分に存在価値を発揮することはできる。これまで民営化された関西、仙台、高松の状況を見ても、"過度でなくかつ過疎でない"空港運営への地元関与は十分に可能であり、「地元が引き続き民営化後の空港経営を主導すべき」とする理由は歴史をたぐっても見当たらない。これまでの日本で行われた民営化事例において、地元自治体・企業は結果的に運営権者と自然な形で協力・協業しており、事業運営上全く問題は出ていない現実があるのだ。
守旧よりも改革を
他方、今回の福岡地元連合は、現在の福岡空港ビルディング(FAB)出資会社である九州電力と西鉄に代表される"地元権限・権益"そのものであり、今回の審査提案に大きな役割を果たしたJAL/ANAもすでに、FABの役員には名を連ねていた。これまでの民営化、すなわち、東急グループに自然な形で地元が融合している仙台や、穴吹興産というひとつの地元企業が筆頭企業として経営権取得を目指した高松の事例とは異なり、福岡は初めて"濃い既存利権の象徴"である地元連合だったと言える。
おしなべて言うと、既存の空港運営には無駄や改善すべき点は多く、必要性に疑問符がつく関連会社がやたら作られ、そこに空港ビル株主会社からOBが役員で送り込まれたりしていた実態がある。収支が厳しくなるとテナントや利用者(エアラインや旅客)に費用を転嫁するという悪しき空港ビル経営の歴史には、複雑に利権関係者が絡んでいる。これを改革するにはしがらみのない新しい経営者が必要なのであって、過去からの企業・人間関係に染まった既存企業が急に大鉈を振るうことは不可能である。
国交省の審査基準に、「関連企業の従業員の雇用の確保」という評点項目がある。空港オペレーションでの必要度に関係なく現有人員の雇用確保を一律に新運営権者に要求するような審査基準は、役所らしいといえばそうだが、現実の民営化後の経営改革には足かせとなることであり、見直しが必要だと思う。
そのような事例も含め、地元が空港経営の主体として継続運営することには、そもそも民営化による改革とは無縁の守旧的な性格がある。これらを勘案すれば、民営化における地元による権限・権益の継続は、基本的に避けるべきだと筆者は考える。