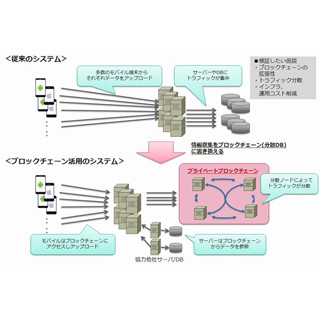最後は、世界のトレンドとなっている最新技術について、日本の現在の立ち位置や日本がまい進できない理由について、パネリストがそれぞれの意見を語った。
平手氏は、製造現場にはさまざまなセンサなどの監視機器が存在するが、それは専用のものを人の工夫でつないで"可視化"したものであり、汎用的なものではないと指摘。すでに海外ではルールに基づいて汎用ワークステーションで実現する例なども出てきており、同じ可視化でも日本の熟練したスキルセットと経験値によるものと、それがない諸外国や企業でもルールが定まれば容易に近いことが実現できてしまうという事実を認識しなければならないとし、日本が参入になかなか踏み込めない理由については、「日本ではIoTが曖昧であるうえ、それに対する投資の負担も不明瞭であるからではないか」と述べた。
山名氏は、「工場の効率化に向けてのICTの活用は進んでいるものの、会社全体の取り組みなのだから、当然経営者トップ自らが、これこそ経営戦略そのものである認識することが大切だ」とし、「機械の故障などを予知して対応することは、製造業のサービスにおける生産性の強化だけでなく、顧客の利便性にもつながっていく」と述べた。
日本の立ち位置については、「いくら技術が入ってきても、結局のところ"アナログとデジタルの融合"である」と断言し、「日本人の持つ、特に製造業での強みとなっている"現場力"あるいは"すり合わせ"を、各部門を越えて行っていくという力が世界での大きな競争力である」としたほか、「中長期の競争力を再復活させるための"日本の製造業の良さ"の見直しも大きなポイントだ」と意見を述べた。現場で培ってきたさまざまなノウハウをセンシング技術の活用によりデジタルに持ち込んで解析するトレンドであっても、”すり合わせ”は必ず付加価値になる。製造業のグローバル化の中において、そうした日本人の特質を出していくというのも必要」と語った。
レグー氏は、「インダストリアルインターネットで重要なのは、製造部分だけでなく組織としての変更管理、すなわちバリューチェーン全体。大きな課題となるのは、組織や部署がその変革を理解するとこと」だと話す。「例えば、高性能3Dプリンタはテクノロジーを代替するものではなく、"ビジネスの創造"という側面から見ていくと、医療現場ひとつ挙げてみても、患者ごとにスキャンを行い、プロファイリングを行うことで3Dプリンタの特性が活きてくる。移植が必要と言われていた人でも、回復期によい治療が可能になれば、移植そのものが不要になるかもしれない。そうした患者にマッチした状況に向けた変革は重要であり、それことが新たなビジネスを生み出す可能性になる」と指摘し、チェーン全体を俯瞰し、ビジネスモデルを構築していくことの必要性を説いた。
それに呼応するように古河氏も、「"すり合わせ"というのは日本国内ではうまくやれているが、インドとすり合わせるということは難しく、考え方を変えるべきだと思っている」とし、判断基準を定義し、その背景を共有しない限り、日本流の"すり合わせ"ではなく、デジタルな意思決定の可視化による共有の方向性が、これからのグローバル展開のやり方になるのではないか」と述べた。
パン氏は、「射出成形というのは、まさに日本の"すり合わせ"の技術だ」と断言。背景として、同社の創業者であるLarry Lukis氏の視点で、図面を見て細かなディスカッションをしながら進めるプロセスはどうしたら早くなるのかということを考え、標準化し、それによって生じるリスクを前提にマネージできるものはマネージさせ、標準化するものは標準化し、国籍や文化の違う人たちがお互いに合意した標準化を中心に、その周りに必要なものについてはそれぞれの地域で組み合わせるという考えがあったことを説明した。
これらの話を受けてモデレータである関口氏は、「"標準化をどうしなければいけないか"というのが議論すべき点だと思う」と前置きし、例としてドイツ最大のERPの会社は、80年代に国内製造業が日本の世界進出によって追いやられた際、「IT部門だけでも共通化しようということで当時登場したSAPを皆で担ぎ、結果的に各社にSAPが入った」と説明。「やがてインダストリー4.0の時代が到来すると、モディファイはしてきたものの根っこには同じシステムが存在するため、それをつなぐことは日本に比べるとはるかにやりやすい立ち位置にあり、それを標準化することで中国やインドなどに展開するというのがインドの戦略になっているのだと思う。日本の場合は企業内にも業界内にもさまざまな縦割り組織が存在しており、それをつないでいくためには何をどうすれば良いのかで困っているのではないかという質問を投げかけた。
この問いかけに対し平手氏は、「サイバーフィジカルシステムというものを人工知能やソフトウェア技術、仮想化クラウドなどを活用したフレキシブルな製造工程を作るとして作りあげることと、ITの観点としてERPを活用し製品情報やライフサイクル、製造システム、ライン制御といったものを統合する流れが1つの有機的、生態系的な塊になり、仕組みそのものが輸出され、世界に伝播していく。これがドイツが国として主導したインダストリー4.0の考え方であると理解している。一方で米国のインダストリアルインターネットは、民間企業がリードしながら異なる産業が相互に接続しているということと、バリューチューン全体のインターネット化でデジタルツインの可視化を加速する。つまり、GEの分析プラットフォーム「Predix」に代表されるように個から企業レベル、あるいはフリートと呼ばれるさらに大きな世界全体でどれぐらい動いている可能性があるかという、個人の視点では想像もしないような大きなスケールでデータを集積して解析をするということから、見識が生まれることだと思う」と述べたほか、「インダストリアルインターネットが、「IoT」ではなく「IoS(Internet of Service)」という新たなビジネスモデルとして認識してみると、日本も経験に基づく手法から、標準化や汎用化といった、これまでとは異なるやり方を進める必要があることを強調した。
また古河氏は、「IoTでつながったあとに何をするのか? というのが重要」とし、つながった先での他社の技術を取り込み、自社製品の強化につなげることがドイツでは強いとしたほか、山名氏は、「現場のノウハウなどをサイバーフィジカルシステムに持ち込み"見える化"を実現するには、エッジコンピューティングを活用することが日本流で、業界ごとにコンパクトなサイバーフィジカルシステムを複数の会社が実践しながら起ち上げていくことが大切だと思う」とした。
このほか古河氏は、「生き残っている中小企業は製造や鋳造が素晴らしいが、自前で解析することはかなりの投資が必要であり、実際には難しい」としながらも、「中小企業は決して"零細"ではなくサイズが中小の非常に強い会社だと考えており、その良さをアナログではなくデジタルに変えていくことを目指している」と語った。
レグー氏も、「コネクテッドデジタルエンタープライズは、データを新しい技術でやり取りしなければならず、製造の"可視化"も必要であるため、中小企業にも大きなチャンスが生まれると思う」とし、グローバルな企業が中小企業の能力を見てコミュニケーションを取ることで、中小企業は閉鎖的だったサプライチェーンから解放され、何千という新たな顧客と接することが可能になり、手工芸や職人などにも新たなチャンスを与えることが可能になるとした。
最後に関口氏は、「データを集めるためには標準化が必要で、それには隠し持つのではなく、企業の大小を抜きに皆で胸襟を開き、データをシェアし、その精度やバリューを高めていくプラットフォームを構築する必要がある。さらに大切なのは、日本が再びガラパゴス化しないように、ドイツやインド、中国、米国などと手を携えてグロバールなプラットフォームに参加する、あるいは日本が主体となってプラットフォーム作りを進めていくことが大切だと思う」とまとめを述べ、「やれることからやっていくことが大切で、今やらないと日本だけが世界の孤児になってしまう可能性も否定できない。民間の活力を活かすためにも、ドイツのように日本の行政もこの分野にフォーカスした新たな政策を打ち出していただきたい」と語り、セッションを締めくくった。