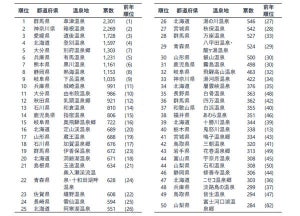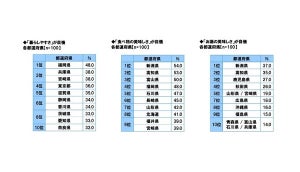東京・神田駿河台の高台には、作家や文化人に愛された"小さなホテル"があることをご存知だろうか。インバウンド需要を受けてホテル業界が活況な中、そのホテルは昭和から続く格調高い空気をまといながら、きめ細かいサービスで訪れる人をもてなしている。そんな「山の上ホテル」(東京都千代田区)の魅力に迫ってみた。
文人がリラックスして"缶詰"できる場所
JR・地下鉄御茶ノ水駅から歩くこと5分。直線的ですっきりとした外観の山の上ホテルが見えてくる。外観から館内の至る所まで"美"を感じる機能的なデザインからは、アール・デコの建築様式ならではの気品が漂う。ホテルの設計は昭和12年(1937)、開業は昭和29年(1954)だが、今見ても新鮮な佇(たたず)まいなのだから、当時、最先端のデザインホテルだったことは想像に難くない。
山の上ホテルと昭和文壇のつながりは深い。川端康成、三島由紀夫、池波正太郎をはじめ、数多くの作家に愛され、定宿として利用されたことでも知られている。それは、出版社の多い神田・神保町が近い立地ということも大きい。
当時はインターネットやメールはもちろん、ファックスもなかった時代。締め切り前になると、原稿を待つ出版社の人々がロビーにあふれかえったという。全館に酸素を補給するサービスは昔からあったようで、きっとホテルにこもって"缶詰"になる時も、まるで自分の別荘のようにリラックスしていたに違いない。もちろん、あか抜けしたしつらえと行き届いたサービスも愛される秘密だ。現代でも著名な作家に利用されているという。
池波正太郎が愛したてんぷらも
全35室という規模でありながら、てんぷら・和食をはじめ、フレンチ、鉄板焼き、中国料理と7つの直営レストラン・バーを設けているのも特長のひとつ。食通としても有名な池波正太郎は、宿泊はもちろん食事だけでも山の上ホテルへ通ったという。中でも、池波正太郎が最も通った店のひとつに「てんぷらと和食 山の上」がある。てんぷらからご飯の炊き加減、みそ汁までお気に入りだったという。
てんぷらのみならず、「鉄板焼 ガーデン」も池波正太郎が愛したレストランだというから、飲食施設のクオリティーはお墨付きだ。昨今、小洒落た飲食店をさまざまな呼び方で表現するが、山の上ホテルの場合、その歴史の深さを思うとやはり"レストラン"という呼び方がよく似合う。
35客室全てが異なる
現在、都市部を中心にホテル業界は訪日外国人客でにぎわっている。和洋折衷の雰囲気を醸し出す山の上ホテルは、さぞかし外国人に人気だろうと思いきや、インバウンドのゲストは限られるという。そもそも、全35室では団体で押し寄せるインバウンド客は受け入れようがない。
時々、欧米の個人客の利用はあるというが、日本人の常連客が主な客層とのこと。山の上ホテルの凛(りん)とした空気感は、選ばれたゲストに愛されていることにも秘密がありそうだ。35の客室は、どれひとつとして同じレイアウトの部屋がない。桜の木肌を生かしたオリジナル家具や手塗りのしっくい壁など、一朝一夕ではつくれない時間と共に存在し続ける質感は心地良さを覚える。
案内板がないのには訳がある
山の上ホテルにいると気付くことがある。案内板がないのだ。もちろん、トイレなどの位置を示す表示はあるが、一般のホテルに見られるような行き先を案内する掲示がほとんどない。代わりにスタッフが随所に立っている。
ゲストの滞在中は、「手助けを丁寧に」を心がけているとスタッフは話す。ゲストとの距離感、空気感が他のホテルと違うのも、スモールホテルならではだろう。歴史あるホテルだからこそ、サービスがルーティンにならないよう、新鮮な接客を心がけているという。心にしみいる見えないサービス心。山の上ホテルの特別感はこうしたさり気なさにも秘密があるのだ。
洋風の中に和風の良さを採り入れるホテル。「和洋折衷」という言葉では安直すぎるが、古い物を大切にしゲストの健康を守るホテルに、宿泊業が最も大切にすべきスピリッツを感じた。「ねがはくは、ここが有名になりすぎたり、はやりすぎたりしませんやうに」という三島由紀夫の言葉が今に生きるホテルだ。
※記事中の情報は2016年4月取材時のもの
筆者プロフィール: 瀧澤 信秋(たきざわ のぶあき)
ホテル評論家、旅行作家。オールアバウト公式ホテルガイド、ホテル情報専門メディアホテラーズ編集長、日本旅行作家協会正会員。ホテル評論家として宿泊者・利用者の立場から徹底した現場取材によりホテルや旅館を評論し、ホテルや旅に関するエッセイなども多数発表。テレビやラジオへの出演や雑誌などへの寄稿・連載など多数手がけている。2014年は365日365泊、全て異なるホテルを利用するという企画も実践。著書に『365日365ホテル 上』(マガジンハウス)、『ホテルに騙されるな! プロが教える絶対失敗しない選び方』(光文社新書)などがある。
「ホテル評論家 瀧澤信秋 オフィシャルサイト」