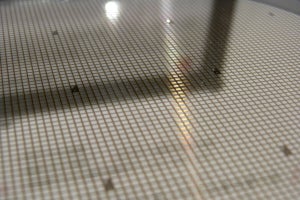UBICの行動情報科学研究所。2014年に設立した研究所では、同社のAI(人工知能)エンジン「KIBIT」をベースに数々のアプリケーションを生み出し、AI技術のビジネス活用を進めている。現在、研究とアプリケーション開発、クラウドインフラ、テクニカルサポート、戦略の5つのチームで構成しており、スタッフ数は65人だ。今回、AI技術に加え、同社における将来的なビジネスの方向性、研究所の戦略などについて、執行役員 CTO 行動情報科学研究所所長の武田秀樹氏に話を伺った。
--2014年に研究所を設立したメリットは?
武田氏:もちろん、研究のための人材は獲得しやすくなった。行動情報科学研究所の前身であるテクノロジー部は、元々アプリケーション製造を主目的として創設された部門だった。それが、技術的競争力の強化を追及した結果、クラウド構築、言語処理研究と、カバーする領域を増やしてきた。その成り立ちゆえに、アプリケーション製造と研究が近く、そこが我々の独自性となっている。これも結果的にはメリットになった。
--研究所で取り組んでいることは?
武田氏:機械学習と自然言語処理に関連する基礎研究および、各種ソフトウェア製品の開発を中心に取り組んでいる。実際に使えるAIの技術にこだわっているので、研究もアプリケーションとしての出口を意識しながら行っている。
AIに過剰な期待を抱くのではなく、何を解決するのかを設計することが重要
--日本におけるAI技術は?
武田氏:これは日本のみの状況ではないが、実際のビジネスに役立つ所にまだまだ落としきれていないと感じている。昨年あたりから、AI技術をユーザー企業が積極的に活用していこうという動きが活発になっているが、データを機械学習で解析すれば、答えが自動的に導き出されると考えられているケースもあり、過剰な期待があるのではないか。実際の業務に適応するためには、何を課題として選ぶか、何を解決するのかを設計することが重要になる。
というのも、人工知能の研究を始めたという話はよく聞こえてくるが、具体的なビジネスの価値を生み出せたという話は、まだまだ耳にすることが少ない。Googleの「TensorFlow」をはじめ、ディープラーニングのフレームワークは増えてきている。また、AmazonやMicrosoftなど機会学習のさまざまなアルゴリズムをクラウド上でPaaSとして使える状況にはなってきている。つまりプラットフォームは選択肢が増えているが、これらは部品であり、オンプレミスにせよSaaSとして提供するにせよ、最終的にアプリケーションにしないと実務では使えない。
このような状況を見ていると、ビッグデータがバズワードだった2012年あたりのことを思い出さざるを得ない。ビッグデータの時は企業のビッグデータをビジネスに結び付け、バリューを出すのはデータサイエンティストの仕事とされていた。
しかし、実際にビッグデータを何らかのビジネスとして結果に結びつけられた企業は、一部の人材とデータに恵まれた企業のみであり、情報を蓄積、高速処理できるHadoopやSparkなどのIT技術の話題だけが先行してしまっていた。データサイエンティストがカバーする領域の一部が、現在はAIのタスクに置き変わっただけだとも感じられる。
同時に今日のAIがカバーしきれていない、そしてデータサイエンティストがカバーするはずだった領域、つまりAIを適応するビジネスドメインの業務知識やアントレプレナーシップといった要素の重要性はいささかも変わっていない。
--AIに対する過剰な期待とは?
武田氏:ビジネスとして成立させるためには費用対効果などを見極めていかなければならなく、われわれはAIの成長を可視化するサービスも提供している。また、経営者向けのセミナーで経営者はどのような観点からAIを見ればよいのか?と問われた際に、AIにすべてを任せて答えを求めるのではなく、活用法を考えるべきだと説いた。
われわれも過去に苦い経験があり、顧客の案件をPoC(Proof-of-Concept:概念実証)まで行い、分析したものをビジネスに役立てることを検討しようとした際、顧客はAI自体がビジネスに役立てることを提示してくれるのではないかと考えており、われわれの考え方と乖離があった。そのため、データを分析できたとしても結果をベースに判断・活用するのは人間であり、技術の限界を見極めつつ活用法をディレクションしていかなければならないと感じている。