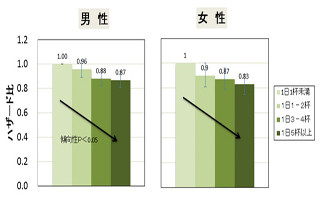国立がん研究センターは16日、これまで生検や手術で採取した組織等を用いて行っていた網羅的なゲノム異常の解析を、血液でも高精度に行える新たな手法を開発し、さらに血液からも進行膵臓がんの約30%に治療標的となり得る遺伝子異常を検出したと発表した。
現在、がんにおける治療標的遺伝子異常の探索には、主に外科的に切除した手術材料や内視鏡的もしくは超音波下に採取した組織が用いられているが、がんの占居部位や病状悪化等で生検が困難な場合もある。また、がん組織に針を直接刺して組織を採取する組織生検は患者の負担が大きく、出血などの合併症の危険性も伴っている。
そのため、患者への負担が少なく、複数回の検査も可能な血液や体液(尿など)を用いた網羅的ながんゲノム解析は、新しいがん分子診断法として期待されていた。しかし、血液検体から得られる遊離DNA(cell-free DNA、以下cfDNA)は少量で、さらにそのうちがん由来のcfDNAは極めて微量であるため、網羅的なゲノム解析を高精度に行うことは、これまでほとんど実現していなかった。
今回発表された同研究では、組織生検等により膵臓がんと診断された患者の血液を用い、膵臓がんに高頻度に異常がみられる遺伝子と、治療標的となり得る遺伝子を含めた膵臓がんのゲノム異常を、低侵襲な検査法である血液(約5ml)から検出する方法について検討。その結果、新たに開発した前処理法を次世代シークエンサーによる解析前に用いることにより、少量(10ng)のcfDNAからも網羅的なゲノム解析を行うことが可能であると確認し、さらに治療標的となり得る遺伝子などの変異14例(約30%)を検出した。
同研究で用いた解析方法は、膵臓がんに限らずあらゆる固形がんで可能であり、また、生検が困難な患者や薬剤耐性獲得変異など経時的な複数回の検査が必要な場合にも有用と考えられ、通常の組織生検よりも患者負担が少ない網羅的ゲノム解析手法として臨床応用が期待される。
また、これまで分子標的薬の開発が進んでいない膵臓がんにおいても、がんの遺伝子異常に基づいた個別化治療が有効である可能性が示唆され、今後さらに検出感度を向上させることで、治療標的の探索だけでなく、難治がんの早期診断への応用も期待されるという。