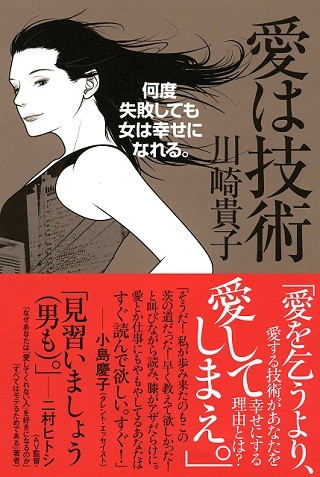「ボクがキミを守る」は男が支配欲に酔っているだけ?
フィクションの世界では、しばしば愛する女性に対して「ボクがキミを守る」的なことをバシッと宣言するのが、ヒロイックでかっこいい男性の振る舞いだとされている。
現実でもそういうことを言いたがる男性(言ってもらいたがる女性)はいるようだが、実際のところ通り魔や強盗に襲われたり、船の沈没や異星人の襲来に見舞われたりしたときに、海猿でもアイアンマンでもない一般男性が、果たして適切に「キミを守る」ことができるのかは、甚だ疑問である。
結局、このセリフを現実で言っちゃうような男性は、「ボクの"守ってあげたい欲"を満たしてくれる程度に、キミには弱い存在でいてほしい(経済的・社会的な立場を大いに含む)」という歪んだ支配欲に酔っている可能性が高いのではないか。
経済的にも社会的にも、お互い自立していたほうが何かとセーフティなこのご時世、対等なパートナーであれば、「危険な目に遭ったら、手を取りあって一緒に逃げようね」で十分なはずだ。
だがしかし、どんなに自分はリベラルで、男女は対等だと思っているつもりでも、表面上は「ボクが守るよ」と言っておかないと、「男のくせに頼りない」と言われてしまうのではないか、という強迫観念が捨てられないから、男の自意識はやっかいなのである。
「男らしくない」ことを、自分で認められない(許せていない)せいで、自己肯定できないまま卑屈になったり、「どうせ女は強くてリードしてくれる男が好きなんだろ」とやっかんだりしてしまう。真綿で自分の首を絞めていく負の思考スパイラルに、男性は陥りがちなのだ。
そして、まさにそんな男性にこそ見てもらいたいのが、7月4日から公開中の映画『フレンチアルプスで起きたこと』である。
「男らしくない自分」を受け入れられない父親の苦悩
この映画は、そこそこエグゼクティブな中流階級のスウェーデン人一家が、フレンチアルプスに5日間のスキー旅行にやってきたところから始まる。夫のトマスと妻のエバは、一見、友達のように対等で仲睦まじい理想の夫婦だ。
ところが2日目、スキー場が人工的に発生させた雪崩が、予想外に大きくなってしまいテラスを襲ったことから、家族に亀裂が走る。雪崩自体は事故未満のちょっとしたハプニング程度で済むのだが、このとき身の危険を感じたトマスは、とっさにエバと2人の子供を置いて、さっさとひとりだけ逃げてしまうのである。
そのせいで残りの4日間、地獄のような気まずさと不和を味わう一家の様子を、この映画はシュールで残酷なコメディとして描く。
トマスは最初、妻子を置いて逃げた事実を、すっとぼけて「なかったこと」にしようとする。「ああ、君の解釈では、僕が逃げたってことになってるんだね。うん、そこは見解の違いだな、アハン?」みたいなクールな態度を気取り、やりすごそうとするのだ。それが、ますますエバの怒りを買って、関係をこじらせていく羽目になる。
おそらく彼は、嘘をついて妻を論破してやろうなどとは決して思っていない。誰よりもトマス自身が、「父親たるもの、いざというときは家族を命がけで守るものだ」という「男らしさ」を内面化し、自分に課していたのだろう。
だから、その「いざというとき」に、自分だけ助かろうと本能的に逃げてしまった「男らしくない俺」を、自分で受け入れ、許すことができないのである。
とはいえ、トマスが最初から潔く「ごめん、逃げちゃった!」と素直に謝っていればエバが許してくれたかというと、それも雲行きが怪しい。
彼女もまた、夫に対して無意識に「男らしさ」「父親らしさ」を期待していたのに裏切られたという被害者意識があるし、「私はその場にとどまって子供たちを守った"母親らしい"女である(あんたと違ってね!)」という自負や優越感も見え隠れする。
男女平等先進国スウェーデンの、一見リベラルで対等に見える夫婦の心の奥にも、「男(父親)たるもの」「女(母親)たるもの」という見えない性役割規範がしぶとく巣食っていることを、この映画は意地悪くあぶり出していくのだ。
湯山玲子と田中俊之が語る"日本のフレンチアルプス"問題
ところで、映画の公開に先立って6月29日に開かれた本作の試写会では、著述家の湯山玲子氏と、武蔵大学助教の田中俊之氏によるトークイベントが行われている。
湯山氏は、『男をこじらせる前に 男がリアルにツラい時代の処方箋』(KADOKAWA)の著者。一方、男性学の第一人者である田中氏もまた、『男がつらいよ 絶望の時代の希望の男性学』(KADOKAWA)を上梓したばかりとあって、男性特有の抑圧や生きづらさを語るには、まさにうってつけの2人だ。
湯山氏はまず、トマスが自分だけ逃げたのを最初「なかったこと」にしようとする態度について、「男性によく見られる思考停止」と指摘。田中氏も、「満員電車のつらさや残業する意味を、いちいち疑問に感じていたら企業で働けなくなってしまう。これまで男性は、自分の本当の感情を麻痺させられてきた」と語る。
田中氏が定年退職した男性に聞き取り取材をしたところ、40年間ひたすら企業に身を捧げてきた結果、自分に何も残っていないことに気付き「残念です」と答えた人が多かった、というエピソードには愕然とさせられた。
また、旧来の男性が「金・権力・女」を原動力に生きてきたのに対して、最近の学生はそこに頓着や執着がないと田中氏は言う。湯山氏は、それ自体はいい傾向であるとしながらも、「金・権力・女」に代わるモチベーションとして、「家族」が再び理想化されていることに危惧を示した。
男性を仕事の奴隷にしてきた戦後社会は、一方で母と子の癒着状態を生み出し、子供を管理/監視したいという「母性の暴走」を許してきたという。その結果、「お母さんに心配かけたくない」という発想が蔓延し、若者が自分の責任で自立や挑戦をすることを阻害しているのではないかというのだ。
たしかに、自分も含めた「いまどき」の男性の傾向として、マッチョな「男らしさ」を手放す代わりに、自分の行動に対する「責任」も取りたくないという甘えを感じることがある。ひょっとすると男性は、「男らしさ」で縛り付けられていないと、責任や主体性を引き受けられないのではないか……そんな暗澹たる考えも頭をよぎる。
自己保身から一転して自己反省の深みにはまり、ダメな自分を受け入れられずに壊れていくトマスの姿を見ていると、そんな男性の本質的な脆弱性を突きつけられているようで、実に居心地が悪い。
しかし、「男(父親)たるもの」「女(母親)たるもの」という性役割規範の暴走は、どちらかがやめれば済むというものではなく、社会の構造や制度が変わらない限り、表裏一体で切り離せない。
本作は、ラストで観客の解釈を試すような「ある事件」が起きて、モヤモヤした不穏な印象を与えたまま幕を閉じる。それは、「トマスが反省して夫婦と家族の絆が修復できれば、それでめでたしなのか?」という疑念を暗示しているように、私には思えた。
ちなみにこの映画、ヒューマントラストシネマ有楽町では、男女ペアなら2,000円で見られる「カップルチャレンジ割引」が実施されているので、勇気ある猛者カップルはぜひ一緒に見てみてほしい。
『フレンチアルプスで起きたこと』
(7月4日よりヒューマントラストシネマ有楽町ほか全国ロードショー)
公式サイト 公式ツイッター 公式フェイスブック
(C)Fredrik Wenzel
<著者プロフィール>
福田フクスケ
編集者・フリーライター。『GetNavi』(学研)でテレビ評論の連載を持つかたわら、『週刊SPA!』(扶桑社)の記事ライター、松尾スズキ著『現代、野蛮人入門』(角川SSC新書)の編集など、地に足の着かない活動をあたふたと展開。福田フクスケのnoteにて、ドラマレビューや、恋愛・ジェンダーについてのコラムを更新中です。