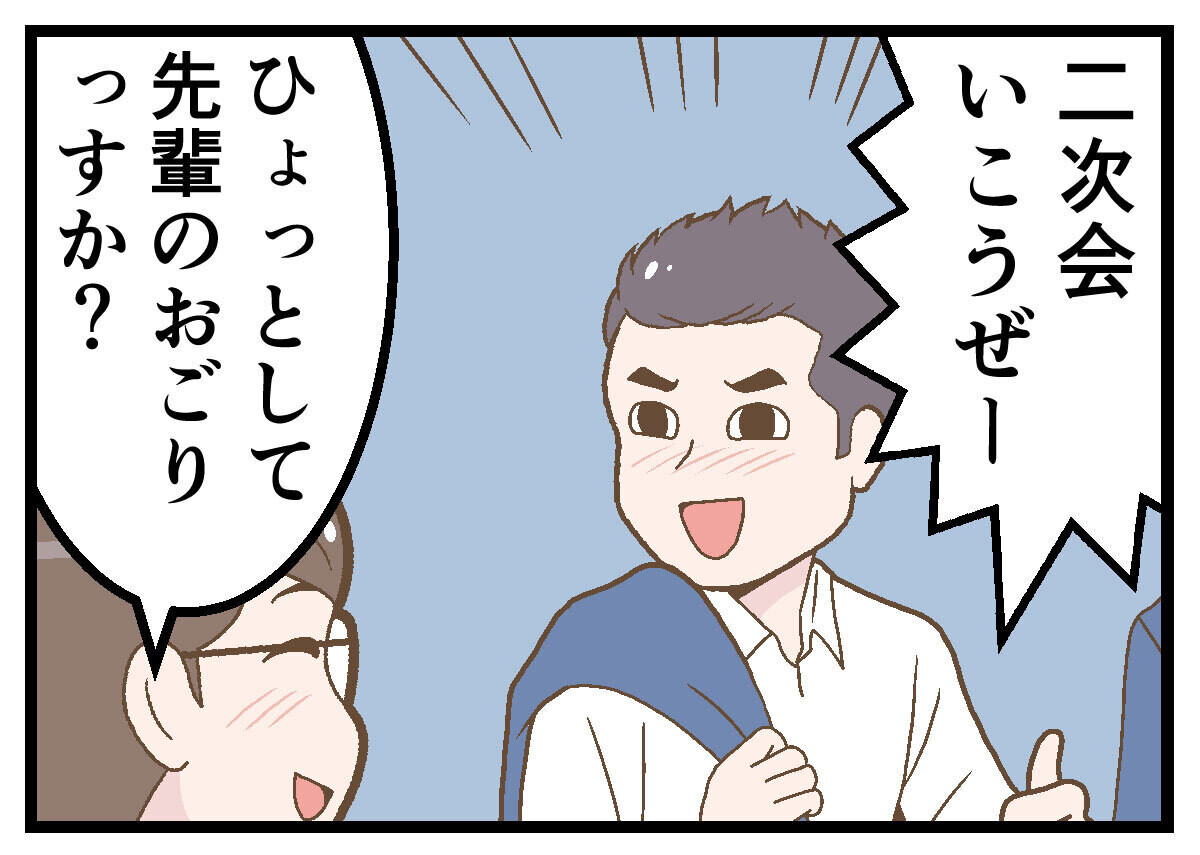新潮社から出版された波多野聖氏の著書『メガバンク絶滅戦争』(新潮社、1,800円(税別))。同書は、いくつもの銀行が合併して誕生したメガバンク「東西帝都EFG銀行」を舞台に、同銀行の名前を「帝都銀行」に変えようとの悲願を持つ頭取と、それを利用しようとする金融庁長官との攻防で始まり、日本国債暴落という状況の中で、米国のヘッジファンドも絡み壮大な物語が展開される。現実の金融業界を強く想起させる同書について、波多野氏にインタビューした。
<『メガバンク絶滅戦争』あらすじ>
「東西帝都EFG銀行」の西郷頭取は、合併前の「帝都銀行」出身。西郷頭取の悲願は、銀行の名前を「帝都銀行」にするというもので、そのために、金融庁長官らとの秘密の会合で、超長期の日本国債を引き受けることを約束する。だが、その後突如として日本国債が暴落。密約を知らなかった「東西銀行」出身で元為替ディーラーの桂専務らの活躍で、一旦は危機を脱するかのように見えたのだが…。米国のファンドなどが買収に名乗りを上げ、さらに混迷を深めていく。メガバンク「東西帝都EFG銀行」はどうなるのか!?
<著者プロフィール>
波多野 聖(はたの しょう)
大阪府生まれ。一橋大学法学部卒。農林中央金庫、野村投資顧問、クレディ・スイス投資顧問、日興アセットマネジメントなどで資産運用に携わる。「波多野聖」名義の小説として『銭の戦争』シリーズ1~8(ハルキ文庫)、『疑獄 小説・帝人事件』(扶桑社)。本名の藤原敬之名義の著作としては、『日本人はなぜ株で損するのか?』(文春新書)『カネ遣いという教養』(新潮新書)『カネ学入門』(講談社)がある。
1990年代、生き残りをかけた銀行同士の闘い
――『メガバンク絶滅戦争』というタイトルですが、タイトルだけ見るとメガバンク同士でぶつかり合う小説なのかな、と思いますが。
現実には、銀行同士のぶつかり合いみたいなものがバブル崩壊以後あるんですね。過去25年を振り返ると、表には出なかったけれども、それぞれが生き残りをかけた、自分たちが本当に生きるか死ぬかという闘いがありました。それまで銀行は絶対につぶれない、そういう存在であったものが、1990年代、いくつかの大きな銀行が破綻します。あのとき銀行マンたちがどういう気持ちや意識で生きていたか、それが書かれている小説がないのではないか、という想いがありまして、そういう部分も触れさせていただいたので、『メガバンク絶滅戦争』というタイトルにしました。
――波多野さんはそのときは、ファンドマネージャーでいらっしゃったんですよね。
投資家として見ていたわけですよ。ファンドマネージャーは投資するわけですから。銀行株を買うべきかどうかという判断になるわけです。当時、僕がファンドマネージャーとして野村投資顧問にいたときも、銀行株をどうするかということが常に議論になっていました。投資家として銀行を見ていて、そういった意味合いで、いろんな銀行のことを調べていたというのは大きかったですね。
"Still Occupied Japan"
――小説の中で長債銀という長期信用銀行の破たんが伏線として流れています。『メガバンク絶滅戦争』の中では、「東西帝都EFG銀行」も、アメリカのヘッジファンドによって危機に陥ります。やはり日本の銀行は、アメリカに勝てないのでしょうか。
金融の自由化だとか、いろんな意味で常にアメリカは日本圧力をかけていたわけです。そういう部分は、僕が非常に典型的な言葉で小説の中に書いた、"Still Occupied Japan"という言葉に表れています。
――「東西帝都EFG銀行」の西郷頭取が漏らす言葉ですね。「まだ占領国ということですな」と続いています。
それは金融機関の人だけでなく、特に財務省の人は感じていることだと思います。
――小説の中で民自党という政党が出てきます。民自党の役割はアメリカの支配下にあることを思い知らせる役割をしてきたんだということが書いてあります。
民自党は、どれだけ進歩的な知識人たちが、政府の対米追随を批判し、安保反対を唱えようと、アメリカ追随をやめなかったのです。
この小説でえぐったのは"日本の本質"
――この小説を読んでいると、どうしても現実の世界を想起させるので、歴史の勉強をしているように、1行足りとも見逃せないという感じがします。
僕がこの小説でえぐったのは"日本の本質"です。日本経済なり、日本政治の本質を、この小説の中であぶり出していることは事実だと思います、フィクションという形で。ノンフィクションでは書けない。ここなんですポイントは。ノンフィクションとしては書けないけれども、フィクションとして書けば、この国の本質をある意味えぐり出して、全部書けるというふうに、僕は作家として気がついたんです。
――この小説では、日本国債が暴落します。現実でも、日本国債暴落というのはあり得ると思いますか。
あり得ると思います。明日来るかもしれない。世界のマーケットが、誰も経験していないようなクラッシュになる。債券の暴落と株の暴落。そこで問われるのは、国債という負債、通貨という負債、みんなある意味では全ての負債の重みというものが、とてつもない形で現実にやってきたときに、本当に何が起こるのかということです。僕もいろんな暴落を経験しましたが、今度来る国債の暴落によって誘発される金融資産の暴落というものが、一体どんな姿で、どんな結果をもたらすのかということを考えるだけでゾッとします。
ブラックマンデーによって、当時のグリーンスパンFBR議長が、徹底的な量的緩和をやり始めて、ものすごい勢いでマネーは増え続けている。金融温暖化と言っているんです。金融温暖化で、本来的に経済に必要なO2ではなく、CO2としてのマネーが強烈な勢いで拡大されて、そのCO2のマネーが金融の中で回り続けて、それが結局ゼロ金利だとかいうような方向をつくり出している。金融温暖化現象なんです。
この金融温暖化現象の限界は誰にもわからないけれど、ゼロ金利が出てきて、さらにマイナス金利が出てきたということは、限界は近いんだなと、普通はそう考えるべきだと思うんです。ということは、我々は限界にきてしまっているんだから、あるところでぶつっと切れるというふうに考えるのが普通でしょうね。
――そうした意味で、この小説は警鐘を鳴らしているということでしょうか。
予言書みたいなものにはなっているでしょうね。金融でもソフトランディング、ソフトランディングと言われる。そんなものはこの世には存在しなくて、必ずあるのはハードランニングなんです。クラッシュとランディングがハードになる。必ずやってくるクラッシュ、企業もそうだし、銀行もそうだし、我々個人も、日本国民としてそれにどう対応するかということを考えなければいけないための書でもあります。そこで僕は、この小説の中で人間関係、組織とは何か、あるいは上司と部下とは何か、そういうことを書いたつもりです。
魅力的なキャラクター設定、関西出身者が数多く活躍
――いろいろ魅力的なキャラクター設定がされていますが、一番魅力的なのは、「東西帝都EFG銀行」専務で為替ディーリングを取り仕切る桂さんですね。
桂はカッコイイですね。僕は自分が銀行の中で役員として残っていたらああなりたいなというのが桂です。昔はああやって腹くくってやる人がいました。この小説を読んだ銀行の多くの方が、ああいう桂みたいな役員がいたら違っていただろうなとおっしゃっていました。
――桂さんは大学教授の息子なんだけれども、相場師ですね。波多野さんの小説には相場師が必ず出ますよね。
僕も相場師だし、ディーリングというものも農林中金で経験して、農林中金に入ったときは相場ということをみんなが言っていました。相場をどう読むとか、相場をどう考えるとかいうことばっかり。
――キャラクターでいえば、関西出身の人が多いですね。
僕自身が大阪出身者で、最初に勤務した農林中金では大阪支店が最初で、同支店に2年半いました。そのときに融資を担当したときに、大阪に本社があった会社がどんどん東京に本社を移していったんです。1980年代。大阪の地盤沈下が始まっていた時代でもあって、大阪を代表する銀行が、本来的にはなくなってしまって、東京の銀行みたいになってしまっている。「立派な大阪は消えたんや」というセリフ、あれは僕の忸怩たる思いとしてあったんです。大阪というものが地盤沈下していって、日本の第2の都市と言いながら、経済の中心からどんどん遠いところに取り残されているというのが感じたというのがあったんです。
「帝都銀行」の名前への強烈な願望が表すものとは!?
――その思いが、関西出身者の活躍に表れているんですね。それと対をなすようにした、この小説の始まりとなる「東西帝都EFG銀行」の名前を「帝都銀行」にしたいという「帝都銀行」出身の頭取の強烈な願望。この思いが、「東西帝都EFG銀行」と日本の危機につながっていくのですが、このような願望は本当にあるものなのでしょうか。
ここが日本人の本質的なところなんです。日本人は名前がめちゃくちゃ好きなんです。例えば、明石の鯛とか、名前に対しての異常なほどの執着心をみんな持っています。
――ブランドということですか。
名前=ブランド。ブランドでも特に名前に固執する。日本人特有のことです。例えば大蔵省だってそうだったわけです。大和時代から続いてきた官庁の名前がなくなるということに対して、何ともいえない寂寥感みたいなものを大蔵省の人たちは持っていたわけです。特に僕が小説に書いているように、帝都グループの人間は帝都ビールしか絶対飲まないし、そういう世界が僕等の時代にはあったわけです。異常なグループ意識、名前意識がすごくあるんだという、そこに安住することの幸福感とか安心感が、常にプライドと一緒にあるんだなと思います。
――帝都という名前に対する異常な執着心。日本人はそうなんですね。それが小説の幹であり、最初に書かれているわけですね。
ファンドマネージャーのときに、日本的なものって何だろうと、ものすごく調べたんです。日本企業を考える上で、何で日本の企業はアメリカの企業とこんなに違うのか、その中で日本的というものの一つのシンボルとして名前、あるいはそういったグループへの帰属意識、名前=家族、そういったファミリー、グループというものへの異常なほどの帰属意識、それは常にあります。
リアリズムの中でのロマンを描いた
――この小説は日本の本質をえぐりつつ、国際的でもありますね。
現実の日本は、常にグローバリゼーションの中にさらされているわけですから、今回はそういった意味あいでヘッジファンド、グローバリゼーションというものを出しました。また、そこにつながってくる情報というものの存在。
――TPP交渉が詰まってきて、交渉が激しくなって、差し出されるのは「帝都銀行」ではないのですが、安全保障のいろんなものが差し出される、TPPの絡みで何かがアメリカに進呈されるような、そういうものも予言されているなと思いました。
非常に大事なポイントです。"Still Occupied"(まだ占領されている)ということがわかっていないと、間違えてしまう、いろんな意味で。
――"Still Occupied"という、あのセリフがそこまで重いんですね。
対アメリカとか、様々な産業政策、金融政策を考えたときに、"Still Occupied"を前提にして物事を考えないと間違えますよということです。僕はリアリストですから、徹底してリアリズムの中で見たらそうなってしまうということです。リアリズムの中でのロマンというもの、さきほど述べた人間というものが持っているロマン、自分が仕事に対してどう考えるか、組織に対してどう考えるかみたいな、そのロマンを日本人どう持つべきなのかということをこの小説で書いた。組織もそうだし、部下、仲間ですね。
――確かに、ロマンを感じました。読後感がいいですね。
青春小説のような感覚。その最後の気持ちよさみたいなものを特に若い読者の人たちに、仕事しようとか、今までと違う形のエネルギーを感じてもらえるのではないかと思います。
――本日は貴重なお話、ありがとうございました。