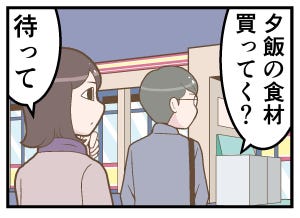今年に入って、ドル円相場は、動きの小さい、いわゆる「低ボラティリティ(変動率)相場」が続いていた。月間の変動幅は1月から7月までの平均で2.90円だった。昨年の月間変動幅は平均4.65円だったから、今年これまでの値動きがいかに小さかったかがわかる。とりわけ、6月と7月の変動幅はいずれも2.00円に満たなかった。
実際の相場変動が小さかったことを受けて、通貨オプションを用いて算出する市場の予想変動率、インプライド・ボラティリティも低下傾向を続けてきた。それが7月の中旬以降、底打ちの兆しをみせている。
ドルは円以外の通貨に対しては、少し前から動意付いていた。6月にECB(欧州中央銀行)が追加緩和を発表したユーロは、ウクライナ情勢の緊迫化によって対ドルで一段と下落。利上げ観測がやや後退した英ポンドも対ドルで値を下げていた。中央銀行が自国通貨高をけん制したり、利上げ観測が後退したりした豪ドルやNZドルといったオセアニア通貨も、対ドルで調整局面に入っていた。そうした結果、ドルの実効レート(※)は昨年9月以来の水準まで上昇してきた。
(※)実効レートは、対各国通貨のレートを指数化して、当該国との貿易量などで加重平均したもの。通貨の総合的な実力と言える。
そして、それにやや遅れた格好で、ドル円も動き始めたかもしれない。7月30日のNY時間にドル円は約4か月ぶりの103円台をつけた。直接のきっかけは、米国の4-6月期のGDP(国内総生産)が前期比年率+4.0%と、市場予想を大きく上回ったことだった。また、その後に発表された、金融政策を決定するFOMC(連邦公開市場委員会)の声明文に、利上げに前向き、いわゆる「タカ派」的な部分があったことも、ドル円を支えたようだ。
今後、米国景気や雇用の一層の改善が示されれば、ドル円は105円を目指すことになるかもしれない。年初に105円をつけていた時の米長期金利(10年物国債利回り)は3.0%だった。現在は2.5%程度だ。したがって、米長期金利が3%に向けて上昇するかどうかが、ドル円が105円を達成できるかどうかの一つの目安になりそうだ。
もっとも、為替市場のボラティリティが高まるということは、材料によっては反対方向にも動きやすくなるということでもある。とりわけ、欧米株価の下落が長期化して投資マインドが冷え込む、あるいはウクライナや中東などの地政学リスクが一段と高まるような局面では、「安全通貨」として円が買われ(ドルが売られ)やすくなる点には留意する必要があるだろう。
執筆者プロフィール : 西田 明弘(にしだ あきひろ)
マネースクウェア・ジャパン 市場調査室 チーフ・アナリスト。1984年、日興リサーチセンターに入社。米ブルッキングス研究所客員研究員などを経て、三菱UFJモルガン・スタンレー証券入社。チーフエコノミスト、シニア債券ストラテジストとして高い評価を得る。2012年9月、マネースクウェア・ジャパン(M2J)入社。市場調査室チーフ・アナリストに就任。現在、M2JのWEBサイトで「市場調査室レポート」、「市場調査室エクスプレス」、「今月の特集」など多数のレポートを配信する他、TV・雑誌など様々なメディアに出演し、活躍中。