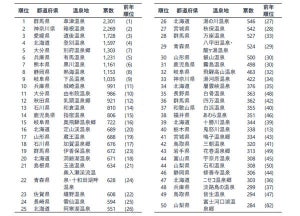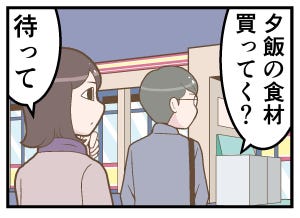5月25日、大阪府高石市の大阪府立臨海スポーツセンター内にあるアイススケート場で1つのイベントが行われた。「臨スポ目標達成御礼スペシャル」。同センター存続の危機を乗り越えたことをあらためて伝える場であり、同センターや関係者、そしてかかわった人々すべてにとって、大きなイベントだった。
臨海スポーツセンターは、いかにして危機を乗り越えたか
閉鎖に至らざるを得なかったスケートリンクも過去に少なくなかった中で、どのようにして存続に至ったか。署名活動や募金など多くの人々の努力があり、もちろんセンターの関係者の奮闘もあった。その上であえて言うなら、「求心力」という言葉にたどりつかざるをえない。
そもそも、臨海スポーツセンターが存続の危機にさらされていたこと、その危機をどのように乗り越えたかの経緯は、広く知られているわけではない。むしろ、知られていないと言ってもいいくらいかもしれない。そのように感じさせられることは少なくない。だからあえて、書きとどめておきたい。
2度にわたって起きた危機
振り返ってみると、存続の危機は2度に分けられる。1つは2008年4月のことだ。橋下徹大阪府知事(当時)の意向のもと、閉鎖案が打ち出されたのだ。その後、署名活動などの反響の大きさから、一度は存続が決まった。
だが、それでおさまりはしなかった。2011年に再び、危機が訪れる。建設されて長い年数がたつ同センターは、2015年度末までの耐震化が必要であった。その工事費は約3億円と見られていたが、大阪府は負担しないとしたのだ。といって、その費用を同センターで捻出するめどはたたない。まさに、閉鎖は現実のものとして差し迫ることになった。
これらの危機にあって、同センター存続に向けた活動の中心となったのが、2004年から2006年にかけ、2年ほど同センター内にあるリンクを練習拠点としていた高橋大輔だった。2008年5月には、同センターでのアイスショーに出演して存続へ向けてアピールするなど努めた。それもまた、13万を超える署名を集めるのに大きく寄与したのは間違いない。
2度目の危機でもまた、高橋は精力的に動いた。2012年5月に松井一郎知事を訪問した際、支援を要請する。すると知事は、「半分を集められるなら」と答えた。つまり1億5,000万円を集められれば、府が残りを負担するというのが府側の"答え"だった。
ただ、1億5000万円という額は小さくない。募金で簡単に集まる額ではないのは容易に想像がつく。高橋も言った。
「正直、厳しいと思います」。一方で、こうも語った。
「あきらめたら、次はないと思います」。
言葉のとおり、高橋は活動を続けた。募金の呼びかけではファンの前で頭を下げ、機会あるごとに呼びかけた。その結果、2013年2月に寄付金1億5000万円が大阪府に贈られ、存続は決まった。
繰り返すが、多くの人々の活動や支援があり、それが実を結んでの現在である。アイスショーに出演するなどして協力した鈴木明子や村上佳菜子、町田樹、さらには募金活動のために駅前に立った田中刑事ら選手たちの存在もあった。と同時に、流れを変えたのは高橋がいればこそではなかったか。
「小さな縁」としなかった高橋の姿勢
トップスケーターであることを自覚し、現役生活にあり、はたからは負担も小さくないように思える中で存続活動に尽力し、その活動の前面に立った。また、厳しい条件ながらも、松井知事から言葉を引き出したのも高橋だ。3億円という巨大な数字とはいえ、わずかながら希望の光が見えた瞬間だったかもしれない。
さらに、高橋のスタンスを示すものとして印象的なのは、最初の危機にあった2008年5月のアイスショーのことだ。当時は、コーチとして信頼を置いていたニコライ・モロゾフとの関係を解消することを発表してまだ間もなかった。ショックが小さいわけもなかっただろうが、そのすぐあとの時期にショーに出演し、笑顔で同センター存続へのアピールに努めたのだ。
高橋が直接、同センターに関わったのは2年。その2年という期間を小さな縁と考えることもできるし、大きな縁ととらえることもできる。そして小さな縁とはしなかったのが、高橋だった。
以前、取材の中でふと、「子どもたちには元気いっぱい、滑ってほしいんですよね」と語っていたのを思い出す。あるいは、シーズン開幕へ向けた練習のつかの間の休憩の時間に、集まってくる子どもたちとにこやかに会話をしている姿も目にしている。
自分が歩んできた道の後に続こうとするスケーターたちへの、あたたかなまなざしがそこにあった。それもまた、同スポーツセンターの存続活動の原動力となっていただろう。そして、「フィギュアスケーター・高橋大輔」の一面を、とてもよく表している。
写真と本文は関係ありません
筆者プロフィール : 松原孝臣(まつばら たかおみ)
1967年12月30日、東京都生まれ。早稲田大学卒業後、出版社勤務を経てフリーライターに。その後スポーツ総合誌「Number」の編集に10年携わった後再びフリーとなり、スポーツを中心に取材・執筆を続ける。オリンピックは、夏は'04年アテネ、'08年北京、'12年ロンドン、冬は'02年ソルトレイクシティ、'06年トリノ、'10年バンクーバー、'14年ソチと現地で取材にあたる。著書に『フライングガールズ-高梨沙羅と女子ジャンプの挑戦-』『高齢者は社会資源だ』など。