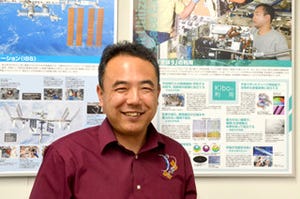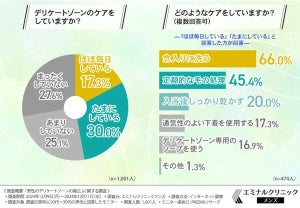一般の企業においても、起案はするものの陽の目を見るまでに時間がかかったり、あるいは頓挫してしまうプロジェクトは星の数ほどあるでしょう。宇宙に行けるようになるまでの気の遠くなるような歳月を、宇宙飛行士の古川聡さんはこつこつと地道な努力で耐え抜きました。
しかし、宇宙飛行士になること自体、そして宇宙へ出て行く究極の環境についての不安はなかったのでしょうか? 話を伺いました。
リスクを許容するためには、正確に把握すること
古川さん:
宇宙へ出て行くことを、人によっては不安に思うかもしれません。その際、リスクを正確に把握した上で許容するという手順を踏んでいくことになります。
私には宇宙で仕事をしたいという強い気持ちがありましたので、多少のリスクが想定されても国際宇宙ステーションに行きたかった。1986年のスペースシャトルチャレンジャー号爆発事故など、打ち上げや帰還の際には100回から200回に1回の頻度で重大な事故が起こっています。ソユーズ宇宙船にも初期にパラシュートが開かず地表に激突した事故がありました(1号、1967年)。その後対策が取られ大幅に改善してはいるものの、そういうリスクがわずかながらある。でも、信頼できる仲間ができるかぎりのことをしてくれたのだからと、許容します。
宇宙に出れば放射線もたくさん浴びます。一日あたり0.5ミリシーベルト、多いときには1ミリシーベルト、地上の約100倍の自然放射線を浴びると言われていますが、一般の人々が発ガンする確率にプラス3パーセントの範囲に線量値が収まるよう管理されています。放射線は女性や若者への影響が大きく、対照的に私のように男性で初飛行が遅かった場合には緩くなりますが、それでもここまでという制限がありますから、やはりとるべきリスクとして受け入れています。
医者から宇宙飛行士へ「転職」
遡れば、私の場合、医者から宇宙飛行士へ「転職」しました。医師としてのキャリアは中断してしまいますが、それまでに培ってきた技術や身につけた知識はきっと宇宙でも活かすことができるだろうと思い新しい道を選んだわけです。医療の現場で同様の行為をしてきたおかげで宇宙での採血や超音波検査にはすぐなじめましたし、心肺蘇生装置を扱った経験を仲間が信頼し、安心してくれた点でも、医師時代のキャリアは役に立ちました。
宇宙飛行士は各自共通して身につける技術や知識もあるのですが、最終的には個々の専門を活かしてチームとして高いパフォーマンスを発揮します。ある人はエンジニア出身で機械に強い、ある人は医師出身で傷病の治療ができる、ある人は軍のパイロット出身で操縦に長けているなど、いろいろな強みを活かし合う。ですから様々な背景を持ったプロフェッショナルがいた方がいい。
今後、月や火星へ出て行く可能性ことを考えると、鉱物学者や地質学者が必要になるかもしれませんね。その場でそれが宝の石なのかそうでないかがパッと見ただけでわかる人材は適任です。
自分は変えられる
私が宇宙に長期滞在していたときの仕事のひとつに、NHKとJAXAの共同開発による超高感度ビデオカメラでの撮影がありました。
オーロラや夜景など、肉眼では宇宙から鮮明に見えるものでも、これまでは光量が足りず、ビデオカメラで撮ると真っ暗にしか映らなかったのですが、この新開発のビデオカメラですと肉眼と同等かそれ以上の鮮やかさになる。『宇宙の渚』というテレビ番組になって放映されていますけれども、そのカメラで映像を何十回も撮る作業が仕事としてあったんです。オーロラや夜景を眺めるのはもちろん楽しい。しかし、それ以上にいい映像を撮らなくてはいけないという大きなプレッシャーがありました。
特に問題となったのはフォーカスです。ちょっとでも油断すると焦点がずれ、くるってしまう。というのは、打ち上げロケット及び宇宙ステーションに搭載するために極力ちいさく設計され、モニターも2インチの極小サイズだったのです。小さいモニターを必死に見ながらノブで慎重に操作しながら対象物にフォーカスを合わせるのは苦労しましたが、ビデオカメラの開発には莫大なコストがかかっていますから失敗はできません。義務感に後押しされてなんとかやり遂げました。
やらされているという感覚になるとやる気は出ないものですが、意義を見出すと奮い立つものです。これは楽しい、ためになるのだ、と。いちばんいいのは、自分自身がその仕事を好きになることですね。実際、私自身もこの撮影が大好きになっていました。
職場環境は必ずしも自分の理想どおりにとはいきません。「過去と他人は変えられないけれども、未来と自分は変えられる」と、よく言います。自分の考えを変えることで自分自身を変え、今いる職場で輝くことができるのではないでしょうか。