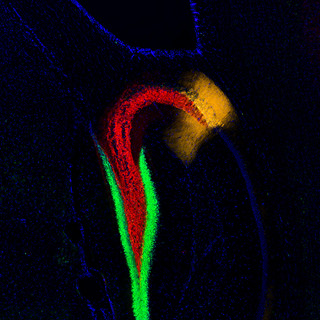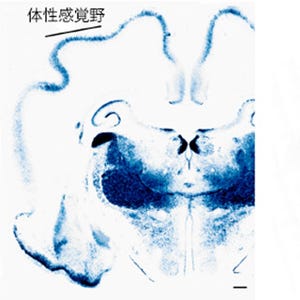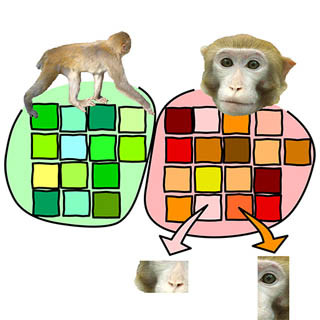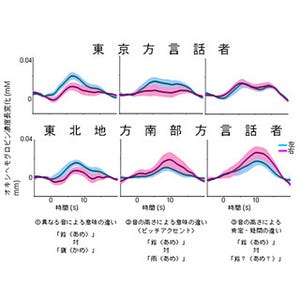21世紀こそが脳の世紀
そしてここまではサイエンス全体の話だったが、続いては「脳科学の将来について」。先ほども触れられたことだが、脳科学はほかの科学の分野に比べて後発である。なぜ後発かというのは、複雑だからだ。1990年代は米国コングレス脳神経外科学会が「脳の10年(ディケイド・オブ・ザ・ブレイン)」と宣言し、脳科学をもっと進展させようということで、それを実施してきた。
現代の科学技術で10年という時間をかけて調べればさまざまなことがわかりそうだが、利根川センター長によれば「たったの10年なんかで脳がわかるわけがない」という。この21世紀こそが(宣言されたわけではないが)、「脳の世紀」ということで、100年をかけてさまざまな発見が続くだろうが、実際には「1世紀程度では全容が解明するわけなんかない」という。そのぐらい脳はわからないものなのだ。
それにも関わらず、日本では、誰がいい出したのかはわからないということだが(税金を分配する人たちらしいが)、日本でもかなりの額を脳研究に投資しており、終わってから10年経つのだから、「もういいだろう」という声が上がっているとする。これだけ投資したのだから、もっとほかのところに投資すべきだと。利根川センター長は、そういう話を聞くと、そんなことをいい出す人は「まったくサイエンスがわかっていない」とした。
また脳科学は、物理学、化学、生物学、数学などで区切れる学問ではないともいう。これらをすべて統合してのみ可能な科学なのだ。将来は、脳科学というのは広く考えると、人文科学や社会科学といわれる、哲学や文学、社会学、法学などすべてを包含した学問になると、利根川センター長は予想する。将来といってもかなり先の話で、100年後ですらならないかも知れないが、いずれはなるだろうという。
その理由は、前述した分野の研究は、すべて「ヒトの脳で行っているから」だ。ヒトの脳で何かが起こっているから、誰かが哲学における発言などをするのである。哲学でも何でも、その思考は脳の中の現象によって起きているからであり、そのこと自体が研究対象となっているというわけだ。
さらに、脳科学は、1人1人の脳の中で起こっていることだけを対象にしているのではなく、もっと広く、脳と脳の相互作用も扱うものだという。社会というものがあり、そこに人間がいて、相互にインタラクションしていて、また外界ともインタラクションしている。脳科学というものはそれらすべてを含めて理解しようという学問であり、少なくとも、BSIではそうとらえているという。そういう意味で、脳科学とは、人間が行うことのすべてを研究しているといっていいというわけだ。要は、「人間とは何か?」を問う科学でもあるのである。よって、あと100年をかけたところで終わりが来ないのが脳科学なのだ。