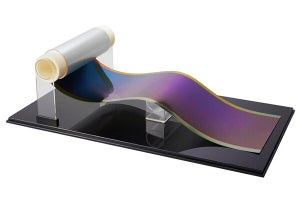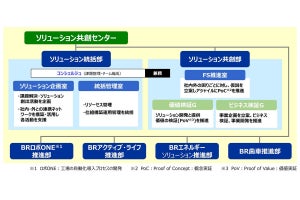社会的弱者に寄り添い現実を描写する
――坂口監督の作品はフィクション/ノンフィクションを問わず、社会的な弱者の側に寄り添う作品が多いという印象があります。あえて俯瞰というか、フラットな視線を避けている印象もあります。
坂口「僕自身の存在からして、権力的なものと拮抗して生きてきました。時には、寄り添うようなそぶりをみせながらも、権力の押しつけは勘弁願いたいと思っていて、それが僕の原動力でもあります。僕は15歳まで鹿児島県の貧しい農家の息子でした。田中角栄の日本列島改造論が話題を呼び、日本中が浮かれていた頃、僕の家族は借金のためにすべての家財を売り払い、家族で逃げるようにひっそりと東京に向かったのです。その時からの東京での僕の泥地を這うような生活が、弱者への共感を育んできたのでないかと思います」
――坂口監督自身がマイノリティであるという自覚があり、マイノリティへの共感が強いのですね。ただご活躍されているテレビの世界は、それとは真逆の世界のように思います。
坂口「確かに、テレビはいってみれば富とメディアという権力の象徴です。そういう意味では、強者の側にもいますが、特に弱者の味方でもあるという両義性があります。その権力の象徴としてのテレビから小さな血管を自らの肉体に引き込んで、そこから運ばれてくる同時代の森羅万象をしたたかに引き込みテレビ番組を作る。そういう中で遭遇する小さな創造の原石の粒を丹念に抽出しながら『映画』を作っていく。善くも悪くも、テレビという毒を自分の中に注ぎ込んでいくような感覚ですね。だからこそ、映画となると命がけです。『夏の祈り』は撮りたいという気持ちだけで、2年間20回以上自費で長崎に通い続け、撮影しました。それならば、テレビ的な絶対安全圏から発信するものとは、まったく異なる偏見、自分という偏見の塊でもって描かなければ、あえて映画として作る意味もないと思います」
――恵の丘長崎原爆ホームですが、原爆劇を学生に向け上演するという部分以外では、一見一般の老人ホームと変わらないように見えたのが意外でした。
坂口「広島や長崎の原爆で目に見えるような大きな身体的なダメージを受けている方は、すでに亡くなっている方が多いのです。映画に出ている方は放射線によってDNAに傷があっても、映像的には、普通の老人に見える方が多かったです。とは言っても、実は、この作品に出演している方々の半分はもう亡くなっています。2年前に撮影したのですが、出演された方の中で、41名もの方が亡くなっています。数日前には、映画の被爆者の3人の主人公のうちのひとりの女性が亡くなりました。悲報を聞いて、大声で泣きたい気持ちに襲われました」
――被爆者自身による被爆再現劇が非常に衝撃的でした。過酷な被害に遭った人々が、その自身の体験を語るだけでなく、演じる。必要以上に残酷なシチュエーションに感じました。
坂口「あの舞台劇は17年前から年に数回、ホームを訪れる修学旅行の小中高生のために行われています。僕は、途中から彼ら自身の演じる必然性を感じて撮影しています。後世に伝えたいという綺麗な言葉ではなく、遺伝子に被爆者としての傷を負っている自分の中の何かを発露しなければ死ねないという覚悟のようなものが感じられました。あの舞台を見た子供たちは皆泣くのですが、僕は最初、感動したり、悲しくて泣いているのだと思っていたんです。でも、それは違いました。被爆した老人たちは、子供たちに被爆という想像を絶する過酷な実体験を遠慮も容赦もなく演じてみせて、結果として泣かしているのです。彼らは、まるでセミが数日間声の限りに啼いて命を散らすように、66年間自分の中に蓄積されたものを限られた時間で充分に発露して劇を終える。そうやって、再び穏やかな日常へと戻るのです。普段は普通に生きていますが、その期間だけ発露しているのだと思います」