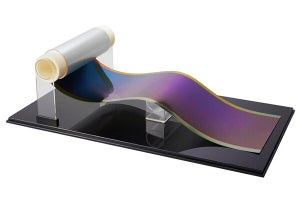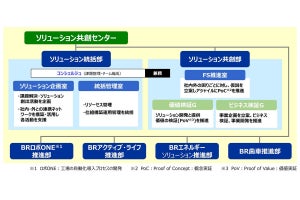他人との関係性の中でスリルを作っていく
――原作もそうですが、今回の映画からは、1990年代初期の地方から見た東京のイメージを感じました。一見華やかな都市に深い闇があり、地方の人が足を踏み入れてはいけない領域に簡単に落ちてしまうという怖さがありました。
阪本「教え子を探して東京の暗部を彷徨うという、原作のロードムービー的な要素を活かしつつ、男と女の12年間の空白をどう埋めるかという恋愛部分にフォーカスして描きました。原作では、爆発とか色々アクションもあるんですけど、そういった部分はあえて描写せずに映画化しました」
――派手なアクションはないですが、窪塚洋介さん演じる中込の印象が強烈です。そのまま東京の怖さとスマートさを体現している人物という印象があります。会社員でありながら、ヤクザよりはるかに得体が知れないというか。
阪本「爆破やカーアクションも映画的だとは思いますが、そういうスリルより中込のような人間との関係性の中でスリルを作っていく方が、僕には向いてるし、やりがいがあると思うんです。その意味で、この作品では言葉も大切ですが、言葉とは裏腹に持っている感情、無言で何かを語るという部分が大切でした」
――ハードボイルドまで行ききらないナイーブな主人公を仲村トオルさんが演じるというのも、意外でした。
阪本「何かが欠落した世間知らずの学校の先生を、いかにチャーミングに見せるかという意味で、演じる俳優そのものの誠実性が大切でした。そのダメさ加減が逆に可愛らしいと思ってもらえるようにするは、仲村トオル君という存在が最適でした」
普通の人間が戦う姿を描く
――この作品で主人公たちが対峙する闇や悪は、悪い意味ではなくてミニマムというか、小さい世界の存在です。阪本監督は、『亡国のイージス』や『KT』では、より大きなものを描いていて、『闇の子供たち』では、もっと救いようのない絶望的な悪や闇が描かれています。そういった存在に対する監督の視点みたいなものは、ある程度一定だったりするのでしょうか。
阪本「例えば、何か自分に暴力性があって、それを映画の中で解消したいと思っても、敵を誰にするのかというのがすごく見えにくい時代です。相手が組織暴力や権力者、何にしても、それを今更過剰に描く時代ではないだろうなと思っていたので、僕はボクシング映画を撮ってデビューしました。今作の主人公は一介の教師で、普段から腹筋しているわでもなく、『ダイ・ハード』みたいな活躍ができるわけでもない(笑)。ただの人間が、自分の存在以上のものと戦う。その闘いが、東京の誰の目にもつかない場所で行われるというのが良いのだと思います。高層ビルが建ち並ぶ場所で、ある種の個人の感情だけで、体を呈して普通の人間が戦うというのを描きたかった」
――ここ数年、阪本監督は非常に振れ幅が広くなってきているという印象があります。今後、どのように作品を撮り続けていきたいのでしょうか。
阪本「硬直したくないというのがあるので、行きずりでいいんですよ(笑)。何かオファーを受けて、やって気づくことも大きいですし。そうやって続けていく中で、前の作品と全く違ったものをやったりして、自分の今までの手練手管が通じないこともあります。その過程で、本当に自分がゼロから作り上げたい企画も生まれてくると思いますし」
――「手練手管が通じない」と感じる瞬間が、最近でもあったりするのですか。
阪本「ありますね。今回の作品のベッドシーンだって、自分が先に照れてるわけですから(笑)。自分の照れをなくすため、男の助監督と2人でベッドに入って、役者に『こんな感じなんだよね』って(笑)。そんな瞬間、沢山ありますよ。『どうやって撮ったらいいんだろう』と迷うことは、10本や20本撮ってきても、まだまだありますね」
――『行きずりの街』を今回DVDで初めて観るという方に、ひとことお願いします。
阪本「今回の作品は、僕を含めて特に男性にとっては、『過去に似たようなことがあったな』と感じる作品だと思います。もちろん虚構ではありますが、どこかでみんなが自分の失敗した過去に対して、それをどうすればもう一度やり直すことが出来るかを描いているので、そこを観て欲しいですね」
――かつて、阪神大震災や、9.11テロがありました。今回、東北関東大震災が起こり、原発事故も予断を許さない状況です。これらを受けて、阪本監督のこれからの表現が、変容していく予感みたいなものはありますか。
阪本「表現は確実に変わりますね。この間、映画の脚本を書いていたのですが、書き終えた瞬間にあの地震が起きて、基本的に全て書き直しですよ。例えば地震そのものを映画の中に取り込んで描こうが描くまいが、それは関係ないのです。ただし、映画は、それが恋愛ものでも喜劇でも、どんなジャンルだろうと、時代と添い寝しながらやっていかなければいけないものだと僕は思っています。直接的に描かなくても、その意識は自然な形で作品の空気として表れると思います。今回の震災で、『まるで映画を見ているようです』って馬鹿なキャスターがテレビで言ってますが、僕らは虚構の中で生きているので、これから自分が作るフィクションの色合いや空気は、変わってくると思います。それが、どういう形で表れるかはわからないですが、フィクションで何ができるかということに関しても、また今後問わてくると思います」
(C)2010「行きずりの街」製作委員会
撮影:石井健