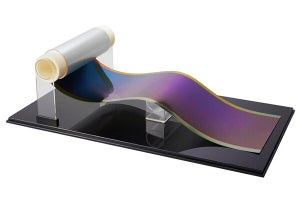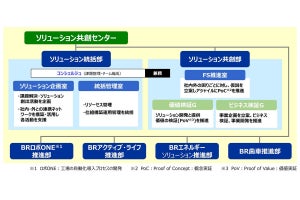役者には、勝手に感じて、勝手に演じてもらう必要がある
――松平斉韶の存在が「悪であるが、悪ではない」という感覚は、画面から強く伝わってきました。
三池「松平斉韶は、そもそも、強靭でも悪人でもない。自分の中で思うことを、正直に行動に移して、しかも逃げは打たず、やった事の責任は自分で負う。それを稲垣さんは理解して演じてくれたのだと思います」
――三池監督は、悪役を魅力的に描くのも得意ですが、今回はどのように演出されたのでしょうか。
三池「演出というか、俺が監督として、殿様と何かを共有したらもう映画として負けだという感じですね。殿様のことなんか、映画監督ごときがわからないんですよ。本当はカメラというのは、そこまで殿様の近くに寄れないという感覚があります。あまりカメラも寄れない、アップがひとつもない、誰がその顔をその位置で見れるんだというような存在がこの作品の殿様で、映画的にはありだと思います」
――斉韶も、役所さんが演じる新左衛門、両者とも、江戸時代になって社会的に武士という存在が必要なくなってきていて、それでもあえて、それぞれの置かれた立場にこだわり死に向かうという印象があります。滅びの美学といいますか。
三池「侍というレッテルや、武士道ということに縛られなければ、我々の中にも、何かそのような感覚はあるはずなんです。違う教典として、それがあるというわけではなく、文化ですから。それは、日々の暮らしの中から出てきたものなので、何かしら共鳴し合う部分はあると思います。そこをあまり引きずり出してくると、何か絵空事を演じなければならない。だから、役者さんの中にも、『きっとこういう人なんだろうな』と思えるような、単にお芝居を超えた雰囲気というのを出して欲しかった。だから、『テロを起こすのは、天下万民のため』という大義名分が、観客にとって嘘に聞こえればいいなというのはありました。もちろん、彼らは動くためにはそう言わなければならないのですが、『それだけじゃない』という臭いが、作品から出てくると良いとは思っていました。ただ、その部分をあまり強調するわけにはいかない。それは観る側の判断と、役者が演じている時にどんなふうに思っているかというバランスですから。映画的には、それを後押しすることも出来るのですが、そこは勝手に感じてもらう、勝手に演じてもらう必要があると思っていました」
――監督の意図というより、観客や役者に委ねる部分が多いのですね。
三池「だって、旗本が今どう思ってるかなんて、俺に聞いてもわからないですよね(笑)。わかったような振りをして演出するには、余りにも自分の中には抱えきれないものがありますから。『自分には抱えきれないということをまず理解している』ということから、この人たちの演じる役に敬意を払って演出したという感じですね」
――理解できないと、認識した上で敬意を払い演出するというのは、興味深いですね。
三池「上から目線で、支配はできないですからね。『これはこう。あなたの役はこう。映画に対する役回りはこう』とかは、まったくしないですね。少なくとも登場人物は映画のために生きてないですから。刺客の12人目だって、11人目だって、新左衛門のためには生きたかもしれないけれど、新左衛門たちが主役の映画を盛り立てるために彼らは死んでいったわけではないですから。その辺は……逆に、敬意を払って演出させて頂きました」