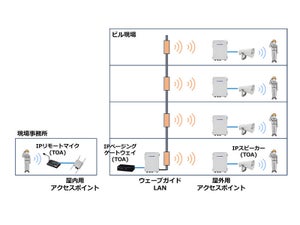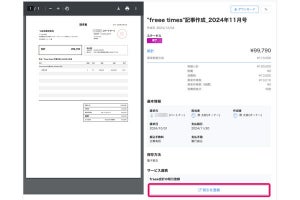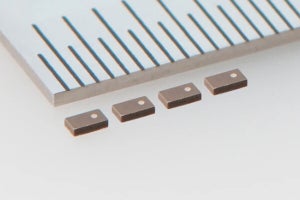カメラマン/撮影監督として、様々なドキュメンタリー映像や日本映画において、輝かしいキャリアを築き上げてきた 山崎裕。彼の初の長編監督作品『トルソ』のDVDが2011年2月4日に発売される。山崎監督がドキュメンタリーで培ってきた独特の感性が活かされたリアルな物語『トルソ』について話を訊いた。
ドキュメンタリー時代から弱者にフォーカスしてきた
――この作品の構想自体は30年以上前からあったそうですね。どのようなきっかけで本作の構想を思いついたのでしょうか。
山崎裕(以下、山崎)「1970年代に女性解放や性解放の運動が盛んだった時期が欧州でありました。イギリスやフランスの普通の劇場でポルノ映画が公開されたりしたのですが、その当時、僕はイギリスに住んでいたんです。今回の映画で登場した人形を、たまたまポルノショップで見かけた時、インスピレーションを受けたんです。これをキーにして、女性からのメッセージを伝えられるような映画を作れないかと思いました。『顔のある男性なんか要らない』と感じていて、生身の男性に入り込めないような女性を主人公に物語を描けると思ったんです。当時の欧州ではそういう女性が変わっていく自由な時代の空気がありました。ロンドンでそんな短編を撮ろうとしたのですが、当時は実現しませんでした」
――30年以上前から構想されていた作品なのに、見事に2010年代の映画というか、現代を反映した作品になっていました。
山崎「1970年代のイギリスの社会状況から離れて、現代の日本で考えたときに、DV問題とかいろいろありますし、いくら当時と比較して女性が自由に自立していたとしても、まだ男性より弱い部分を引きずっています。今の日本だからという事を考えてこの作品を作りました」
『トルソ』
|
|
|
|
化粧もせず、飲み会にも参加せずに、静かな生活を送る独身OLのヒロコ(渡辺真起子)。恋人も友達もいないヒロコの心に拠り所は、顔も手も足もない、男性型の人形だった。彼女の規則正しい日常は、妹のミナ(安藤サクラ)が部屋にやって来たことによって、揺らいでいくのだった |
|
――時代背景的な部分だけでなく、普遍的な部分で、山崎監督はかなりのフェミニストなのではないかと作品から感じました。女性や、マイノリティに向ける視線がとにかく優しいですよね。
山崎「そうですね。やはり僕がドキュメンタリーを長年撮影しているせいかもしれません。やはりドキュメンタリーでは、弱者にフォーカスして取材することが多いですから。あと、僕自身、家族の中で末っ子だったというのが大きいのかもしれません。戦後民主教育の中で家族に守られて育ち、何というかアメリカ映画で描かれるようなマッチョイズムに対して、幼い頃から拒絶反応のようなものがありました」
カメラの前では、すべてがミクロな世界
――山崎監督は「ルワンダ大虐殺」など、世界的にも大きな事件を題材にしたドキュメンタリー作品も撮影されています。そのようなマクロな題材と、今回の映画のようにミクロな題材とがあるわけですが、描かれるとき、監督の中で視点の違いはなどはあるのでしょうか。
山崎「基本的にカメラというのは、ミクロな世界なんです。どんなに大きな題材や対象を撮影していても、目の前に見えているものしか撮れない。大きな国際問題を扱ったとしても、僕の目の前にいる人と、目の前にある風景しか、映像で語れないのです。そういう意味では、常にミクロな視点であるというのは変わりません。カメラの宿命みたいなものですね。テーマとしてのグローバルな視野とか、客観的な広い視野があっても、撮るのは目の前の個人です」