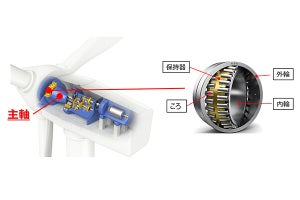サブカルなものをメジャーに変える
――やはり、ネタ探し的な視点で、小説やマンガといったほかのコンテンツを見てしまうものですか?
川村「映画プロデューサーと名のつく人は仕事ですから、多かれ少なかれ、そういう目で見ていると思います」
――その時、プロデューサーとして作品のスケール感まで考えるのですか? 予算や監督やキャストも含めての話なのですが。
川村「そうですね。その自分だけの妄想中が実は一番楽しいんですよ。その妄想が確実に面白く膨らめば、メジャー映画になるという事です」
――『DMC』の場合はどうでしたか?
川村「"これは映画にならない"と皆に思われるような作品を映画にするという事に興味があったんです(笑)。『DMC』の原作を読んだ時、"これはメジャー映画では無理。少なくとも東宝では無理だろう"と感じたんです。セリフや歌詞に"殺害"はあるし、"レイプ"、"親など殺せ"とか、もうとんでもない(笑)。そこにまず、ひっかかりました。つまり"これどう映画にするの?"という視点からスタートしたんです」
――そこからスタートして、映画化で意識した部分などはありますか?
川村「企画コンペの段階で決めていたのは、サブカルでカルトな原作をメジャー映画として成立させたいという部分ですね。『DMC』の原作の魅力はギャップ。この映画をそのまま単なるサブカル的な文脈で映画にするなら、僕がプロデューサーとしてやる意味はない。だから、王道の、メジャーの青春映画として成立させようと思った。あとは、スパイダーマンのようなアメコミヒーロー的な側面。クラウザーII世の奇抜な衣装が成立するのは、アメコミヒーローの世界だと思ったんです。弱い少年が持て余す能力を手に入れて苦悩するという、ヒーロー的な部分も表現したかった」
――それから具体的にどう、キャストやスタッフを決めていったのでしょうか?
川村「主役は松山ケンイチさん以外は考えていなかった。これは狙い通り、成功したと思います。もし、映画を褒めなくても、この作品の松山さんの演技は誰もが褒めると思います。彼はとにかく凄かった。彼も、不可能と思われるような役を演じる事を面白がってくれる役者さんなんで、そういう部分でこの難しい役を引き受けてくれたんです。スタッフも考えましたね。この作品は3つの要素だと思ったんです。『ギャグ』、『音楽』、そして『感動ドラマ』。まず、『感動ドラマ』の脚本を、ウェルメイドなドラマが得意な大森美香さんにお願いして、『ギャグ』の部分をバラエティ出身で人を笑わせる演出の名手である李闘士男監督に。『音楽』に関しては重要なライブシーンが多いので、ライブカメラマン出身の中山光一さんにお願いしました。あと音楽は、カジヒデキさんやK-DUB SHINEさん、ジーン・シモンズといった各音楽ジャンルの"本物"で周囲を固めました。3つの要素を総力戦で成立させようとしたんです」
――ショートコントの連続のような原作や、現実離れしたキャラクターを、1本の実写映画としてまとめる、成立させる難しさはありませんでしたか?
川村「キャラクターで言うと、あのマンガのクラウザーII世の白塗りを実写で成立させるという事が難産でした(笑)。衣装やメイクのディテールには、本当に苦労しました。音楽の部分も、『あれは、本当のデスメタルではない』といわれますが、その通りで、それをメジャー映画でそのままデスメタルとして表現すると、観客が楽しめないと思ったんです。あと、主人公の感情の見せ方は、とにかく丁寧に考えて映像にしたつもりです」
――実際にそうして完成された映画ですが、手ごたえはありましたか?
川村「実は、映画を観に来ていた観客の8割ぐらいは原作マンガを読んでいないお客さんだったんです。そこは本当に狙い通りでしたね。この原作を映画化した意味があったと思いました。サブカルの原作モノを観に行くのでなく、堂々と王道のメジャー映画を観にいくというスタイルが成立したと思います」
――王道のメジャー映画といいますが、下品で不謹慎なギャグは原作のままですね。
川村「不謹慎な笑いは好きですね。僕は、元々、不謹慎なもので笑いを教わったんです(笑)。だけど、最近の日本映画ではそれが少ない。海外では『メリーに首ったけ』のファレリー兄弟とかいるんですけど、そういうのがメジャー映画として成立して、堂々と映画館で皆が楽しんでいる。『DMC』はそういう作品になったと思うので、嬉しいですね。あれだけ"殺せ"とか"ファック、ファック"言ってる映画ですからね」
――川村さんはプロデューサーとしてDVDにも関わっているとのことですが、DVD化にあたり、どんな部分に注力したのですか?
川村「80分の作品の撮影ドキュメンタリーが入っています。あとは、劇中のDMCのライブシーンが完全ノーカットで収録されています。この映画は、カオスというか、音楽とギャグのグチャグチャな感じがエネルギーとして集まっている作品です。DVD特典では、それを1個1個解体した要素が特典として入っていると思います。何というか、映画作りの要素が閉じ込められているので、とても面白いと思いますよ」
――松山ケンイチさんと、松雪泰子さんは、この作品で日本アカデミー賞にノミネートされましたね。
川村「作品自体がギャップのギャグなんで、このノミネートすらも冗談みたいで……。アカデミー賞と一番遠い所にある映画なんで、授賞式で役所広司さんの横とかに、どんな顔で松山ケンイチさんが立つのか、考えるだけで面白いけど、申し訳ない(笑)」次のページでは、川村プロデューサーが日本映画界の現状を分析。