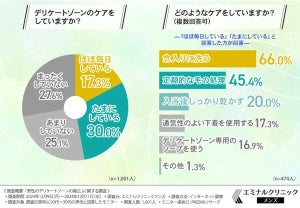"日常"とはかけ離れた"非日常"の空間と捉われがちな美術館。その美術館のひとつである水戸芸術館現代美術ギャラリーが、"日常"をテーマにした展覧会『日常の喜び』を開催中だ。会期は2009年1月18日まで。
本展は日比野克彦や宮島達男、藤浩志、梅佳代といった国内外14組のアーティストが参加しているグループ展で、作家それぞれの独特の視点が捉えた日常という概念や状況であるかっこ付きの「日常」を作品として展示している。
本来アートは普通の人々の、普通の日常の空間の中にあるべきだろう。ところが、美術館やギャラリーという場所は、その日常から離れた非日常の特別な空間だと感じさせるところが少なくない。多くの人々が、敷居が高い、威圧的な感じがすると、美術館に足を運ばない理由をあげるのも、頷けるところがある。もちろん美術館を"特別な空間"、"大切な場所"と思う人も多くいるわけで、それはそれでとても大切な事なのだが、それ故に、一般の人々から"遠い"と思われてしまっては、美術館の存在意義すら危うくなる。その美術館に、あえて"日常"というテーマを持ち込んだ本展の意味するところはどこにあるのだろう?
参加作家14組の作品には一貫性がない。本展の説明にもあるように、「"日常"というテーマをさまざまな角度から扱った、絵画、映像、インスタレーション、立体、写真など」の、実にさまざまな考え方や表現手法でアプローチされた作品ばかりで、まさにそれぞれの作家が考える日常が表現されていると言えるだろう。考えてみればアーティストが日常とは関係がないわけはなく、彼らも彼らの日常を生きているはずで、そうした作家たちが持つ"日常"に対する感覚がこれらの作品に現れているのかもしれない。しかし、それはやはり一般の感覚とはちょっと違っていて、ユニークだったり、驚きがあったり、アーティストならではの新鮮な感覚にあふれていて面白い。
多様な作品ばかりの同展だが、作家たちの日常に対してのアプローチの仕方には、大きくいくつかのパターンにわけてみることができる。
写真や映像で表現した作品には、直接的に日常が関わっているものが多い。ガイ・ベンナーは、あっと驚くような"舞台"を使って、ウィットとユーモアに富んだ家族の日常を描いた映像作品『スティーリング・ビューティ』を出品している。家族の間に起きる、まさに橋田壽賀子のドラマか中学生日記のようなストーリーが、キッチンやリビングを舞台に繰り広げられるのだが、実はこの映像、グローバルに展開している大手家具量販店の店頭でゲリラ撮影したもの。売り場なので当然、家具にはタグがついているし、通りかかった一般客が「このカメラなに?」とレンズを覗き込んでしまうシーンもある。
また、心なごませる日常の"決定的瞬間"のスナップを集めた梅佳代の『シャッターチャンス!』や写真を通じて茨城県大子町の人々と交流する事で、その日常を撮ることができたというマルコ・ボーアの『太子アーカイブ』、作品の主体は服だが、過去と現在の家族の関係性を表すものに写真を用いた西尾美也の『コスチュームプレイ』のように、どの作品も写真や映像を通して、直接的に日常が描かれている。
|
|
|
梅佳代『シャッター&チャンス』日常を撮らせたら随一の写真家が"決定的瞬間"をとらえた未発表作品 |
マルコ・ボーア『大子アーカイブ』EUジャパンフェストの写真プロジェクト「日本に向けられたヨーロッパ人の眼」の一環として撮影された |
こうした直接的に"日常"を描いている作品に対して、日比野克彦のダンボール作品の数々は言うまでもなく、テーマや素材などから間接的に日常を感じさせる作品も多い。その辺にある土(泥)を素材に使って描いた淺井裕介の壁画『泥絵 大犬』は、圧倒的なエネルギーが壁面にぶつけられており、これのどこから日常を感じろというのか? と疑問が沸き立つとともに、描く事という浅井の"日常"がそこに現出している事に気がつき、再び驚く。対照的にシャープペンの芯を使って作った電信柱が立ち並ぶミニチュアな世界を構築した岩崎貴宏の『ディファレンシャル / インテグラル カリキュラス』に、ミクロな世界と格闘する岩崎の"日常"に驚いた。また、アトリエに転がっていた工具を使って、24時間分の時計表示を組み立てた森田浩彰の『クロックワイズ』は、作品を通じて、時間という日常を描いている。
|
|
|
常に描き続けているという淺井の作品は水戸駅前の歩行者デッキの柱にも出現した。描く事が彼に取っての"日常"という事か |
岩崎貴宏『テクトニック・モデル』まるで工事現場のように見えるが、建物は文庫本、そびえるクレーンは文庫本のしおりをほどいて作ったもの。驚異的なミクロな都市の風景だ |
もうひとつの大きな傾向が、「遊び」という"日常"に深く関連した作品が多いという事だ。とりわけ、いらなくなったおもちゃを取り替えっこするフリーマーケット「かえっこ」からあぶれたおもちゃを素材として作り上げた、藤浩志の空間インスタレーション『Happy Forest』は興味深い。あぶれたおもちゃ(つまり、誰もほしがらない不運なおもちゃ)のほとんどが大手ファーストフードのおもちゃセット(作家曰く、Happy系)で手に入るもので、あぶれたおもちゃだけでほぼ自然発生的にこうしたインスタレーションが生み出されるのは、この「かえっこ」がアートとして人々の日常と深く関わっている証と言えるだろう。
|
|
|
藤浩志『ハッピー・フォレスト!』 |
作品を説明する藤浩志氏。ぶら下がっている紐状のものは、チョコレートの包み紙をつなげたもの。彼の奥様がかえっこ会場から送られてきたおもちゃを次の会場に転送するための作業を行う際のストレス発散の産物とのこと |
この他、KOSUGE1-16は、実際に鑑賞者が自転車を漕ぐ事で、周りに作り上げられたコースをミニチュアの自転車がジェットコースターよろしく走るという、ゲーム性の高い体験型アート作品『KOSUGE フォルダー_01~スポーツパーク~』を出品した。建築家集団のアトリエ・ワンは、「美術館に来た人すべてがアートに見たくてきているのだろうか?」という疑問から、美術館の中で堂々とマンガを読むために制作した 本棚と閲覧空間が融合した『マンガ・ポッド』を同展に持ち込んでしまった。さらに、誰もが子どもの頃から親しんだ折り紙を超絶技巧の匠の域まで引き上げた折り紙作家・神谷哲史が出展作家に加わっているのは、同展が現代美術の枠を外してしまう楽しさにあふれている事を如実に表しているようだ。こうした日々の生活の中にある素材や遊びから、"日常"を感じさせる作品こそが、アートが日常にある上でもっとも意義ある存在に感じた。
同展では、このように日常に対する多様な価値観が、美術館という空間で具現されており、展示空間いっぱいに楽しさ、面白さがあふれている。実は日常というのは、つまらない平々凡々としたものではなく、その日常を感じる感覚によっては、日常がひっくり返るほどの面白さ、楽しさを生み出すポテンシャルを持っているという事を感じた。実は美術館ではわれわれの感じる"非日常"そのものが"日常"なのかもしれない。