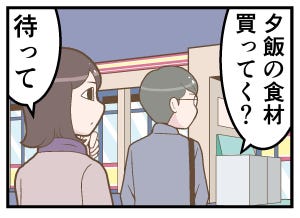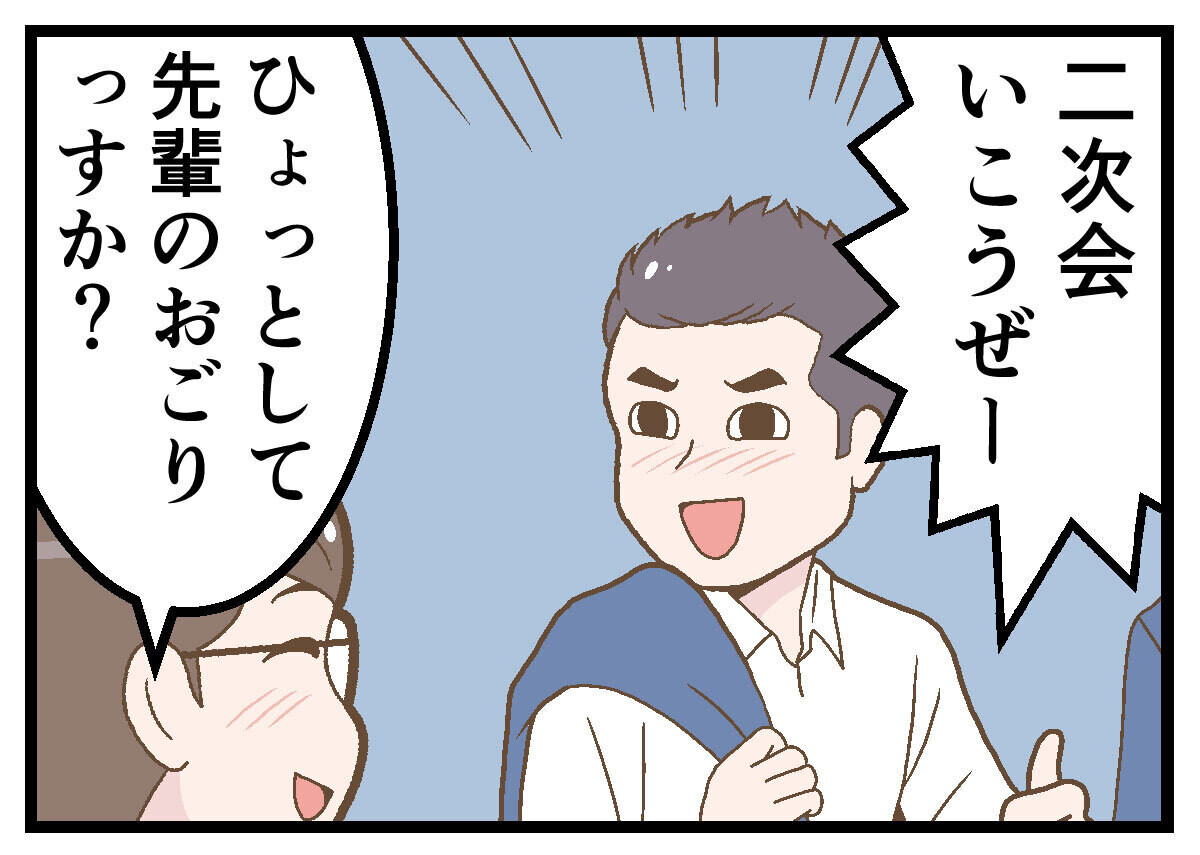経済協力開発機構(OECD)が21日に発表した、OECD加盟諸国の所得格差を調べた報告書で、日本における所得格差は過去5年間で縮小に転じたことが分かった。
調査は、OECD加盟先進国30カ国を対象に、過去20年間の所得格差を比較したもの。所得格差の指標を表すジニ係数のOECD平均は0.311。もっとも格差が少ない国はデンマークの0.232で、もっとも格差が大きかったのはメキシコの0.474だった。また、日本を含む4分の3以上の国が過去20年間で格差が拡大していると報告されている。
日本のジニ係数は0.321で世界平均をわずかに上回った。この数値は0.323を示した10年前の1990年代半ばとほぼ同じ水準で、20年前の1980年代半ばの0.304よりはわずかに格差が拡大したことになるが、2000年前後の数値である0.337に比べ、過去5年ではやや改善されたことを示している。
一世帯あたりの所得では、日本の平均所得は過去10年間で減少。また、日本の下位10%の国民の平均所得は6,000米ドル(購買力平価)で、OECD平均の7,000米ドルを下回り、日本の上位10%の平均所得も6万米ドルと、OECD平均の5万4,000米ドルよりも遥かに高い水準を示した。
その一方、「貧困水準(所得分布の中央値の2分の1未満で生活する人の比率)」で日本はメキシコ、トルコ、アメリカに次いで4番目に高かった。
報告書ではこうした日本の格差の原因のひとつとして、急速に進行する高齢化社会を挙げている。OECDの調査では、過去20年間で高齢者の割合は2倍に増加し、子供の数は3分の1に減少したと報告している。
そのほか、世界的な所得格差の傾向では、55~75歳の高齢者の貧困に改善が見られる一方で、成人若年層や児童の貧困の増加が指摘されている。日本では1985年以降、66歳以上の人の貧困率は23%から21%に減少した反面、子供の貧困率は11%から14%に増加したと報告されている。
報告書では、こうした世界的な所得格差拡大の流れに対して、先進諸国では政府が増税と歳出増により歯止めをかけていることを評価する一方で、こうした政策は一時しのぎにすぎず、若年層の雇用を確保し、良好なキャリア見通しを提供する方法に政策を転換すべきだと提言。特に今日の労働市場が求めるスキルが身に付けられるような教育のあり方に目を向けるべきだとしている。